 備忘録
備忘録 Google AI Pro特典のクラウドクレジット活用術!Vertex AIで透かしなしの画像を生成する方法
Google AI Proの特典として付与されるGoogle Cloudクレジットの賢い使い道を解説する。Vertex AI経由で次世代モデル「Nano Banana Pro」を利用すれば、一般向けツールで強制される視覚的なウォーターマークを回避し、商用品質の4K画像を生成することが可能だ。
 備忘録
備忘録  備忘録
備忘録  備忘録
備忘録  備忘録
備忘録  備忘録
備忘録  備忘録
備忘録 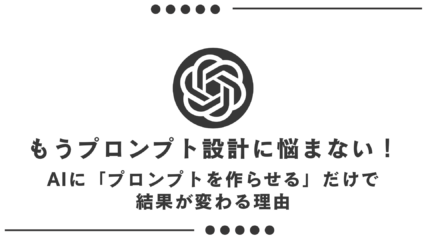 備忘録
備忘録  備忘録
備忘録 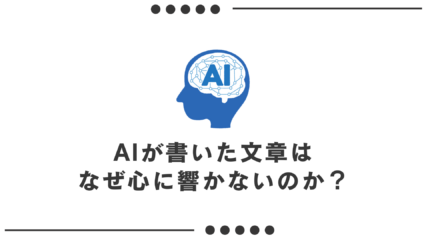 雑記
雑記  備忘録
備忘録  備忘録
備忘録 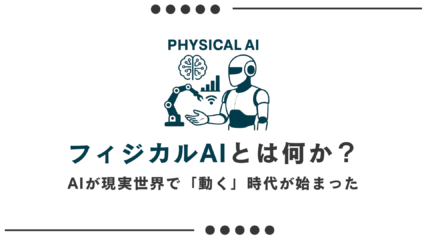 備忘録
備忘録 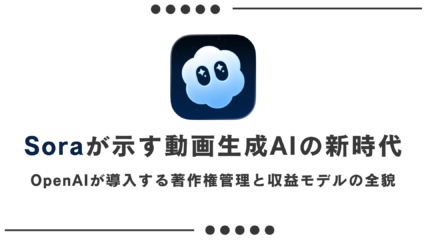 学びと解説
学びと解説  学びと解説
学びと解説  学びと解説
学びと解説  学びと解説
学びと解説  学びと解説
学びと解説  備忘録
備忘録  雑記
雑記 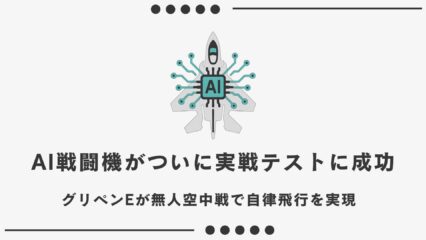 備忘録
備忘録 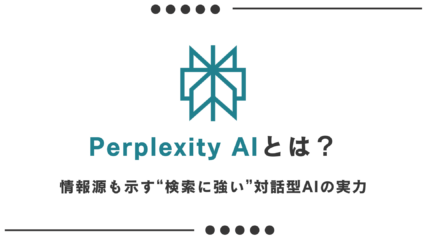 備忘録
備忘録  備忘録
備忘録  備忘録
備忘録 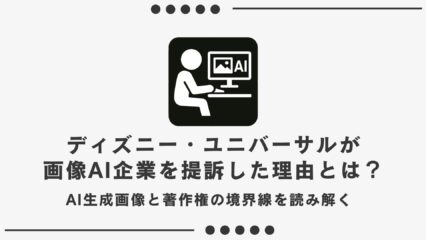 備忘録
備忘録  備忘録
備忘録  備忘録
備忘録 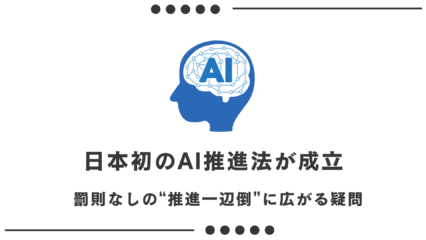 備忘録
備忘録  備忘録
備忘録 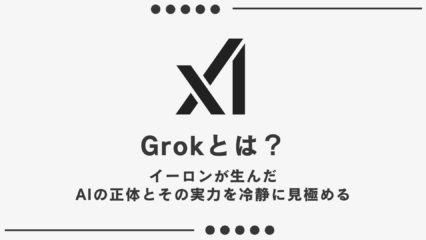 備忘録
備忘録 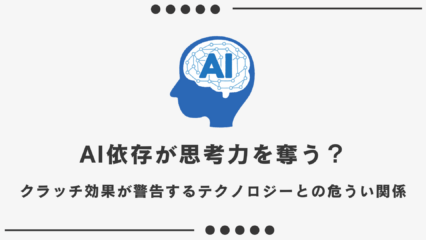 備忘録
備忘録