はじめに
ある日、YouTubeを眺めていると、どこかで聞いたことのある声がAIによって再現されている動画を見かけた。
まるで本人がしゃべっているかのように、しかも本人が一度も演じたことのないセリフで。
「これ、本当に大丈夫なのか?」
そう疑問に思ったのは私だけではないはずだ。実際、経済産業省がついに動いた。
AIによる声優・俳優の“無断学習と利用”に対して、具体的な違反事例を示したのである。
この記事では、声優のAI音声をめぐる法的リスクと、それが私たちの創作活動や日常生活にどのような影響を与えるのかを、私の予見と知人の実体験を交えて解説する。
無断で声をAIに学習させるリスクとは
まず押さえておきたいのは、AIに声を学習させること自体が違法とは限らないという点だ。ただし、それが「本人の承諾を得ていない」場合は、不正競争防止法に抵触する恐れが出てくる。
具体的には、以下のような行為が問題視されている:
- 声優の声を無断でAIに学習させ、その声で別人の楽曲を歌わせて動画サイトにアップロードする。
- 有名俳優の声を模したAIボイスを搭載した目覚まし時計を製造・販売する。
経済産業省はこれらを「著名表示冒用行為」「周知表示混同惹起行為」に該当する可能性があると指摘している。
法律がカバーする範囲とは?イラストや他ジャンルにも波及する可能性
この問題、実は声だけの話では終わらない。
「イラストやキャラクターデザインにも同じような保護が及ぶのではないか?」
SNSで交わされるこんな声には、私も深くうなずいた。
事実、知人のイラストレーターも「自分の絵柄をAIが模倣している広告が流れていた」と憤りを語っていた。
彼女は商業案件を多く手掛けていたため、実害も大きかったという。
つまり、「創作された個人の表現」がブランドとみなされる時代に突入しているのである。
AIクリエイティブ時代の落とし穴:あなたの創作も知らぬ間に利用されているかも?
身近な例でいうと、YouTubeやTikTokのショート動画で「ハチワレをAIで歌わせてみた」というコンテンツを見たことはないだろうか?
一見、無害なファンアートに見えるが、これも原作や声の持ち主の許可がなければ、違法性が生じる可能性がある。
とくに商業的に利用された場合、そのリスクは跳ね上がる。
AIの進化により「できること」が増えた一方で、「やってはいけないこと」との境界はますます曖昧になっているのだ。
実際にあった“ひろゆきボイス”広告の問題
知人の話をもうひとつ紹介しよう。ある企業が、ひろゆき氏のAI音声を無断で使用した広告動画を出していた件である。
彼女はその動画に不快感を覚えたと語っていたが、法律的にもこのケースはグレーを通り越してブラックに近い。
明確に「誰の声か」が分かる場合、それはもはや匿名性の裏に隠れることはできない。
悪意がなかったとしても、法は「意図」ではなく「結果」に対して裁きを下す。
まとめ
AIの発展に伴い、声や絵といった「人の表現」を巡るトラブルは今後も増加すると予想される。
声優や俳優のAI音声を使うことは、技術的には可能でも、法的・倫理的なハードルが高く設定されているのが現実だ。
「好きだから」「面白いから」といって軽い気持ちで投稿した動画やアプリが、思わぬ法的リスクを招く可能性がある。
これからの時代、創作の自由と権利の保護をどう両立させるか。
そこに私たち一人ひとりのリテラシーが問われている。
参考リンク
- 生成AIと著作権に関する考え方(文化庁)
- AIによる模倣行為に関する注意喚起(経済産業省)
- 不正競争防止法の概要と改正ポイント(特許庁)
- 生成AIに関するガイドライン(総務省AIネットワーク社会推進会議)
- ひろゆき氏のAI音声広告問題報道(ねとらぼ)
- イラストレーターの作風模倣とAI画像の著作権問題(ITmedia)
- YouTubeのコンテンツ利用ポリシー(公式)
- AI音声合成と倫理問題に関する海外の視点(MIT Technology Review)
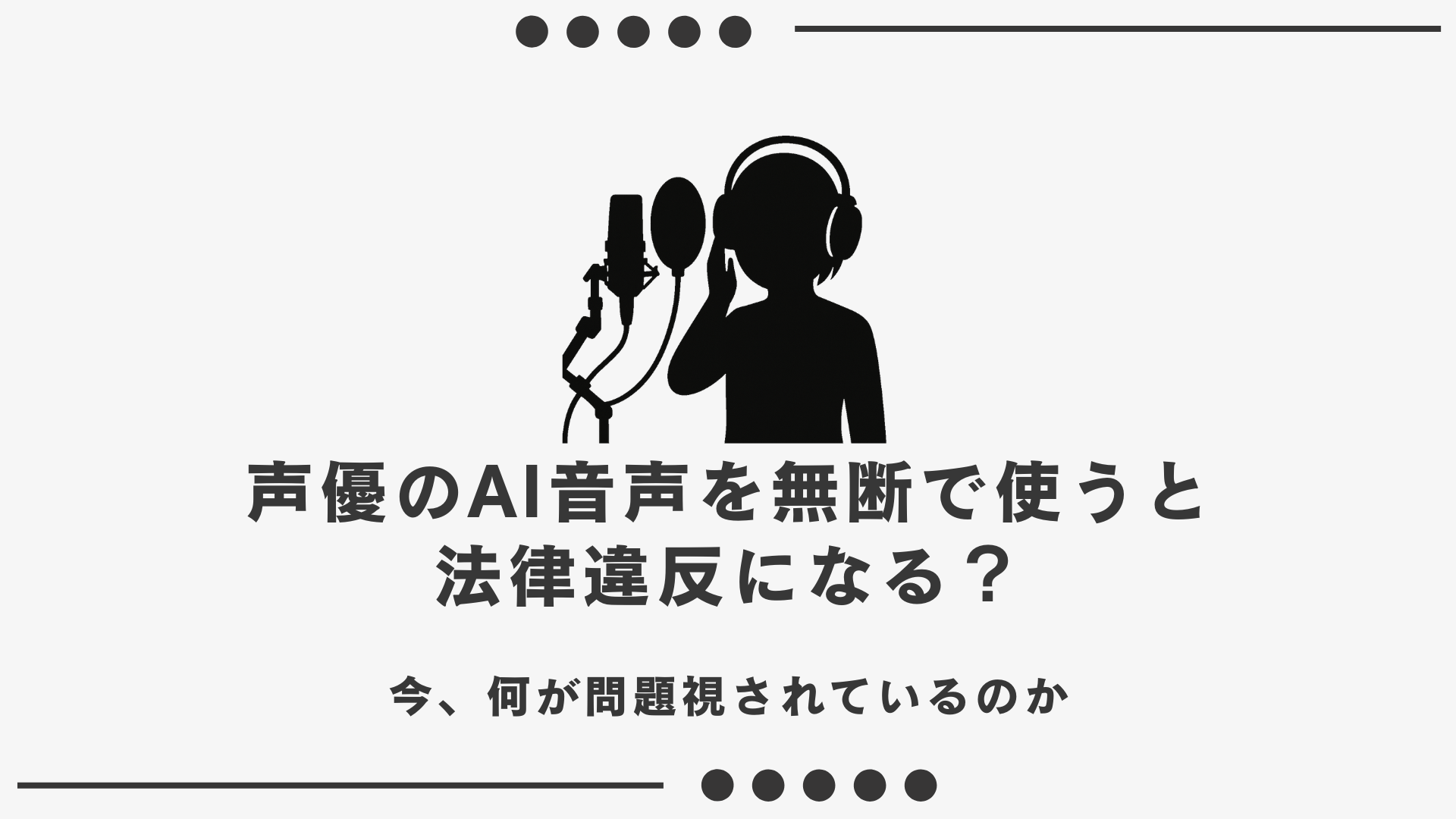


コメント