はじめに
近年、AIが生成したブログ記事やSNS投稿が、目に見えて増えてきた。
ニュースまとめ、商品レビュー、エンタメ系の話題まで、あらゆるジャンルで、AIによって出力された、いわゆる“ポン出し文”が氾濫している。
確かに読みやすい。誤字脱字もなく、要点もきちんと押さえている。だが、どこか物足りない。読み終えたあとに、なぜか記憶に残らない。
理由は単純。「人の声」がないのだ。
今回は、「AIライティング」が進化した今だからこそ、人間にしか書けない文章とは何か、そのヒントを探ってみたい。
AIポン出し文は“正しすぎて”面白くない
AIは非常に優秀だ。常に最適解を出そうとするし、情報も豊富に持っている。
けれど、そこに意外性やズレは存在しない。予想外の展開もなければ、読んでいて「おっ?」と思わせる瞬間も少ない。
人間が面白いと感じる文章には、「ツッコミたくなる余白」や「引っかかり」がある。
逆にAIの文は、整いすぎていて、ノイズがまったくない。結果、驚きも感動も生まれにくい。
文章とは、正確さだけで成り立つものではない。
むしろ、ちょっとした脱線や違和感が、記憶に残る“味”になる。
AIには体験がない。だから「匂い」がしない
最大の違いはこれだ。AIには「体験」が存在しない。
恋愛で傷ついた夜、深夜バスで一人泣いた旅、怒鳴られて悔しかった新人時代。
そういった人間らしい経験が、文章の奥行きを生む。
AIが失恋について書いても、一般論や定型表現が並ぶだけ。
けれど人間の言葉には、自然の風景、街の様子、人の営みなど、五感で感じられる目に見える場面を表現した具体的な情景が宿る。
そこに、読者は共鳴する。
つまり、文章に“におい”や“手触り”を与えるのは、経験に裏打ちされたリアリティなのだ。
情報はある。でも、行間が読めない
AIはとにかく丁寧だ。何でも説明しようとする。
だが、その“親切すぎる”姿勢が、文章から「余白」を奪ってしまう。
人間の書く文には、あえて説明を省くことで生まれる“読者の想像力の余地”がある。
たとえば、「あのときの彼の顔を、私は今でも忘れない」。この一文に、すべてを説明する必要はない。読者は勝手に情景を想像する。
AIはここを読み取れない。すべてを明文化しようとする。
その結果、味気ない“情報の羅列”になるのだ。
AIには「書きたい衝動」がない
AIは頼めば文章を書く。だが、それは「命令されたから書く」という動機にすぎない。
一方、人間が書く理由は、もっと根源的な衝動による。
「誰かに伝えたい」「言葉にしないと苦しい」「思わず吐き出したくなった」
そんな動機が、文章に熱を宿す。
この“内側の熱量”こそが、読み手の心を動かす。
AIの文章がいくら巧みでも、なぜか響かないのは、こうした衝動が欠けているからだ。
AIを「代筆者」にするな。「整形ツール」として使え
AIを使うことそのものは悪くない。むしろ推奨されるべきだ。
筆者自身、よく校正や誤字チェック、構成の整理に利用しているが、抜群の力を発揮してくれる。
だが、最初から丸投げしてはいけない。
書く内容、伝えたい意図、文章の芯を作るのは人間だ。
AIはその「下書き」を磨くツールにすぎない。
この役割分担を見誤った瞬間、文章は“うまいけど空っぽ”になる。
ポン出しの時代は終わった。これからは「分業」の時代
少し前までは、「書ける人」が重宝された。
だがAIの登場により、“誰でも文章が書ける時代”になった。
その中で差がつくのは、「何を書くか」「どう語るか」の部分だ。
文章の土台は人間が作り、構造や体裁の整備はAIが補助する。
これが、これからの文章術における理想的な分業モデルとなる。
創作とは本来、孤独な作業だ。しかし今は、AIという「編集者」がすぐ隣にいる。
この存在をどう活かすかが、書き手としての真価を問われる部分になる。
まとめ
AIは便利だ。間違いなく強力な味方だ。
実際、筆者も全ての文章をAIでチェックしている。
だが、そこに込める“意味”や“温度”は、自分の中からしか生まれない。
AIが形を整える。人間が意味を作る。
この関係性を正しく理解しなければ、どれだけ読みやすくても、心に残らない文章になってしまう。
ポン出し文に足りないのは、構成でも語彙力でもない。
人間の衝動と、経験に裏打ちされた言葉だ。
これからの書き手に求められるのは、ただ書くことではない。
AIでは書けない“芯”を持った内容を、どう伝えるか。
その一点に尽きる。
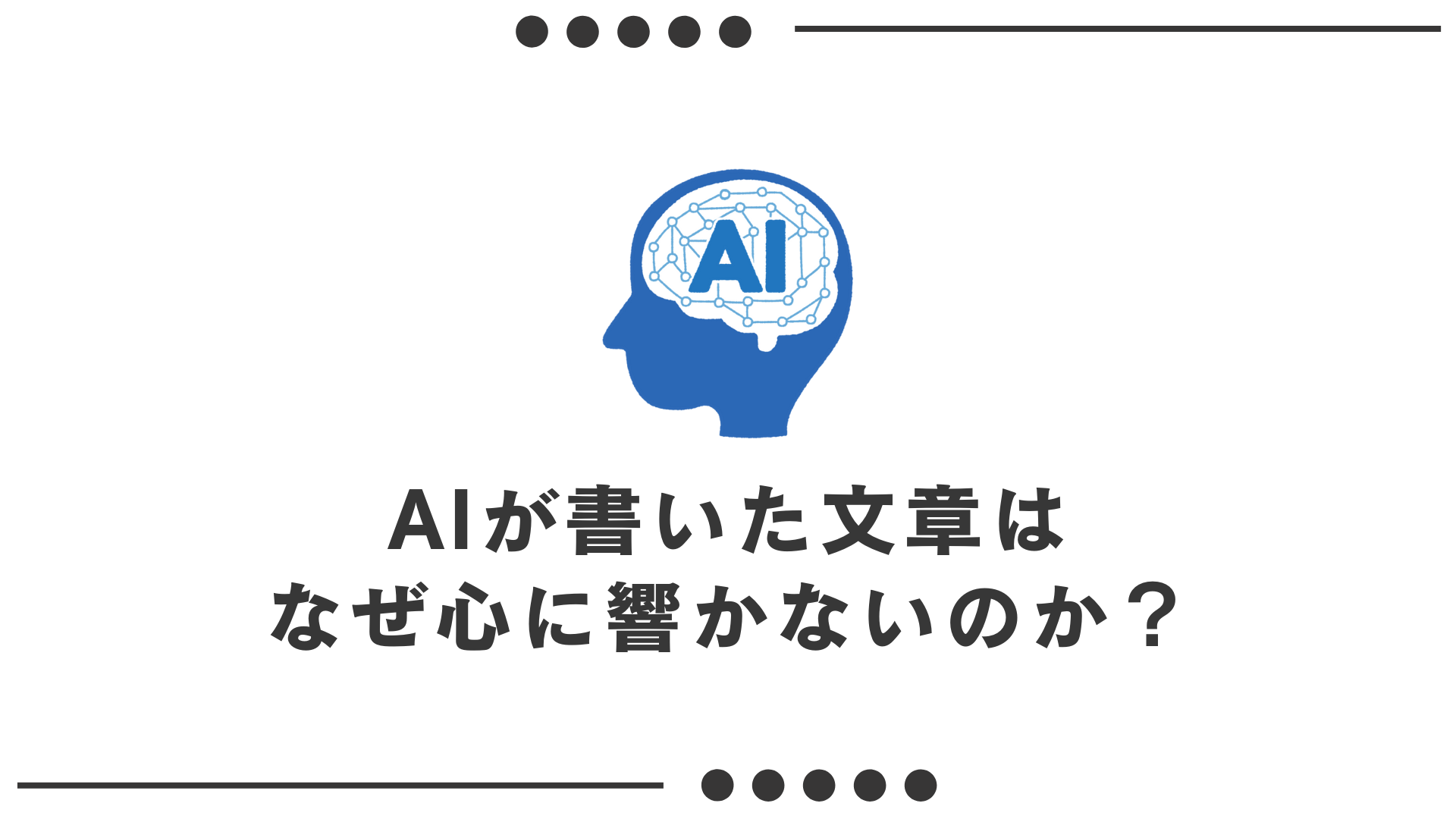
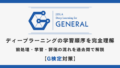

コメント