はじめに
G検定では、ディープラーニングの基本的な仕組みや用語の理解が問われる。中でも「学習の工程」に関する設問は、頻出かつ取りこぼしやすいポイントだ。
本記事では、実際の過去問を例に取り上げながら、ディープラーニングの学習工程を整理する。学習・評価・前処理といった一連の流れをしっかり押さえて、試験対策と実務への応用に役立ててほしい。
問題:ディープラーニングにおける学習の順序は?
ディープラーニングでの学習工程では一般的に以下を繰り返す。順序として、最も適切な選択肢を選べ。
選択肢は以下のとおり。
A) データの前処理
B) モデルの評価
C) モデルの学習
- C, B, A
- A, C, B
- A, B, C
- B, A, C
正解は「A, C, B」
各ステップの意味を正しく理解しよう
A) データの前処理
学習工程の最初に必要なのが、「データの前処理」。
これは生のデータをモデルが学習しやすい形式に整えるプロセスを指す。
具体的には以下のような処理が含まれる。
- 欠損値の補完
- 正規化や標準化
- ラベルのエンコーディング
- 画像のリサイズやグレースケール変換
このステップを怠ると、どんなに高性能なモデルでも精度が出ない。
つまり、モデル学習のスタートラインは「整ったデータ」からということだ。
C) モデルの学習
前処理が完了したデータを使って、ニューラルネットワークに学習させる。
この段階では損失関数(ロス)を基準にして、重み(パラメータ)を調整するプロセスが繰り返される。
- フォワードプロパゲーション(順伝播)
- ロスの算出
- バックプロパゲーション(逆伝播)
- パラメータの更新(例:SGD, Adam)
この一連の流れは「エポック」と呼ばれる単位で何度も繰り返される。
目的は、モデルが与えられた入力から正しい出力を予測できるようになることだ。
B) モデルの評価
学習が進んだら、次に必要なのがモデルの評価だ。
評価には「検証データ」や「テストデータ」を使用する。
ここで確認するのは以下のような指標だ:
- 精度(Accuracy)
- 再現率(Recall)
- 適合率(Precision)
- F値(F1スコア)
過学習(オーバーフィッティング)していないかどうかを見極める重要なフェーズだ。
評価結果に応じて、学習済みモデルに改善が必要であればハイパーパラメータを見直したり、学習ステップを再度実行することもある。
この流れが「学習サイクル」と呼ばれるものである。
なぜ他の選択肢が不正解なのか?
選択肢を一つずつ検証していこう。
| 選択肢 | 説明 | 誤りの理由 |
|---|---|---|
| C, B, A | 学習→評価→前処理の順だが、前処理が最後では意味がない。 | モデルに生のデータをそのまま渡すことになり、不適切。 |
| A, B, C | 前処理→評価→学習という順。評価が学習より先になっており、手順として成立しない。 | 評価には学習済みモデルが必要。 |
| B, A, C | 評価→前処理→学習の順。評価が最初では学習対象が存在しない。 | 初手の評価にはモデルが必要なので順序が逆。 |
このように、順番を正確に理解しておくことが試験合格への鍵となる。
学習工程のサイクルは実務にも直結する
G検定の学習で得た知識は、AI開発の実務にも直結する。
実際のプロジェクトでは、以下のようなループが繰り返される。
- データ収集と前処理
- モデル構築と学習
- 評価と改善
- 本番適用と再学習
このサイクルを「PDCAサイクル」にたとえることもある。
単なる知識としてではなく、実装フローの理解として身につけておくと応用が効く。
まとめ
ディープラーニングの学習工程は、以下の3ステップから構成される。
✅ ステップ1:データの前処理
✅ ステップ2:モデルの学習
✅ ステップ3:モデルの評価
この順序は試験対策としてだけでなく、AI開発の基本としても非常に重要だ。
G検定では、こうした基本を問うシンプルな問題が頻出する。
だからこそ、確実に理解し、答えられるようになっておこう。
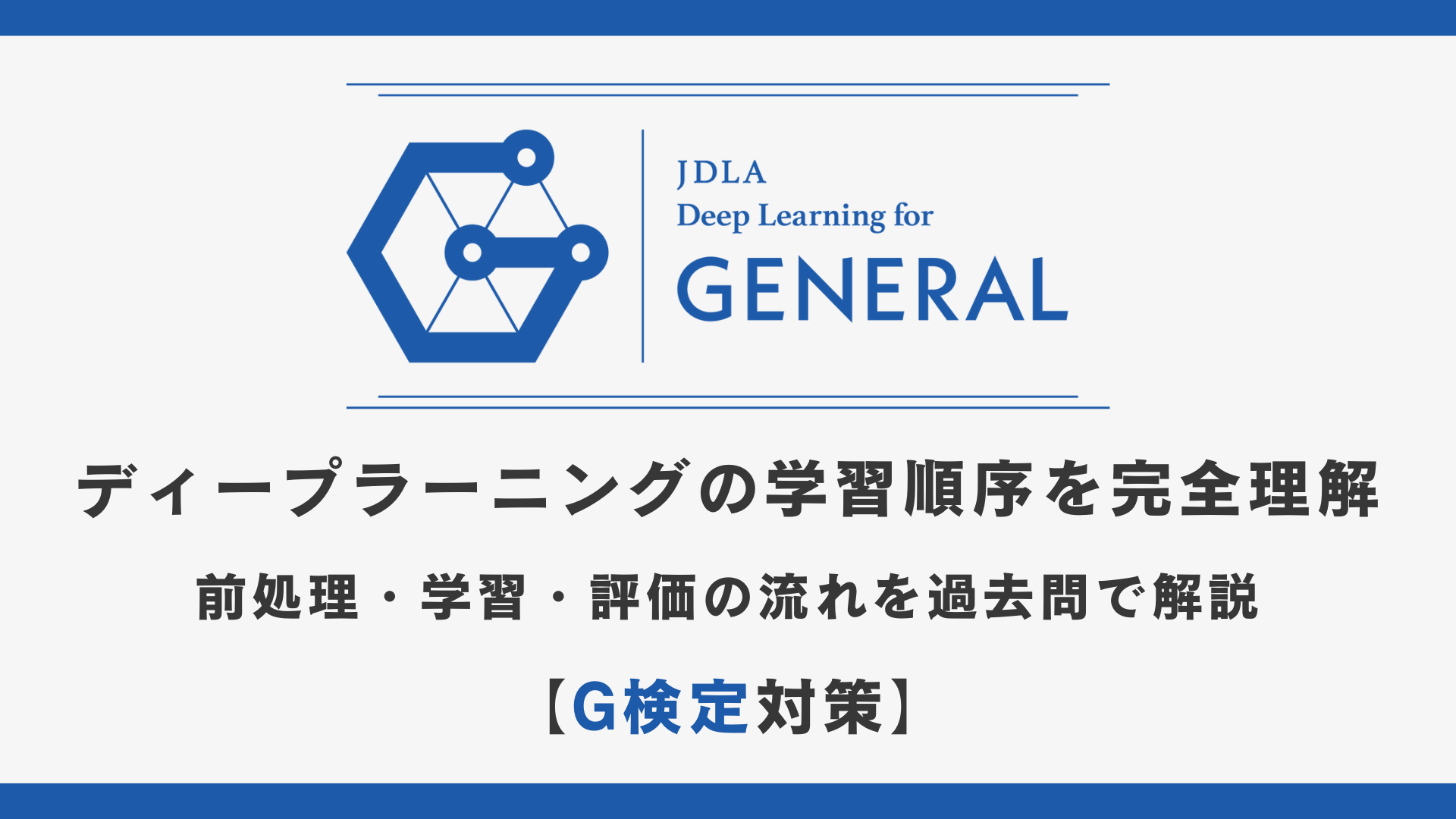


コメント