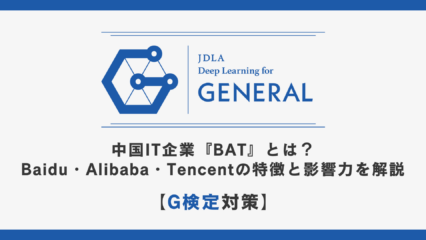 G検定対策
G検定対策 中国IT企業『BAT』とは?Baidu・Alibaba・Tencentの特徴と影響力を解説【G検定対策】
中国の主要IT企業「BAT(Baidu、Alibaba、Tencent)」は、AIやフィンテック、クラウド分野で世界的な影響力を持つ。G検定でも問われるこの3社の特徴や事業内容を解説し、Appleとの違いを明確にする。試験対策だけでなく、実務にも役立つ情報をまとめた。
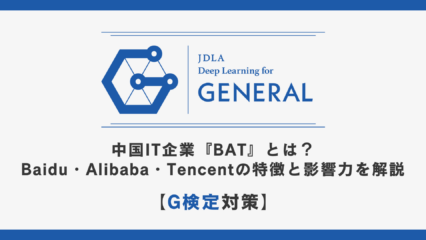 G検定対策
G検定対策 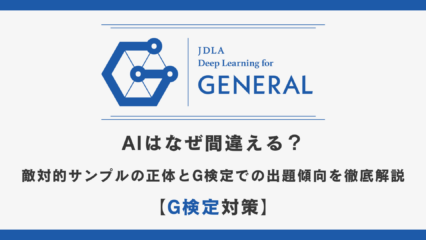 G検定対策
G検定対策 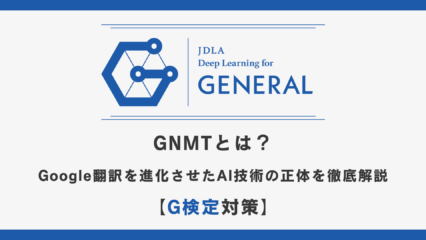 G検定対策
G検定対策 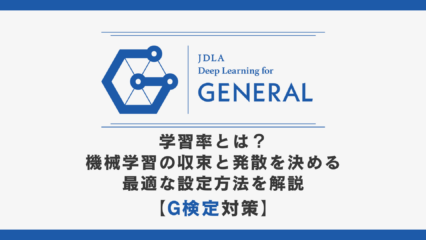 G検定対策
G検定対策 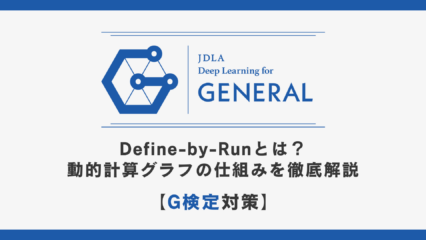 G検定対策
G検定対策 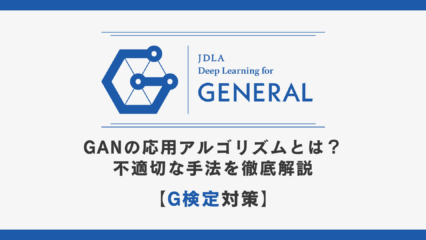 G検定対策
G検定対策 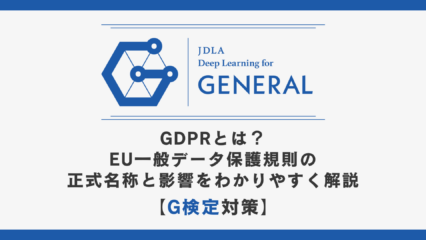 G検定対策
G検定対策 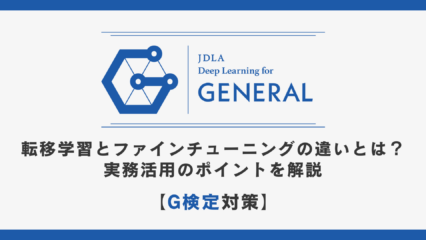 G検定対策
G検定対策 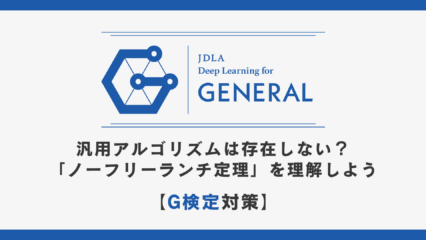 G検定対策
G検定対策 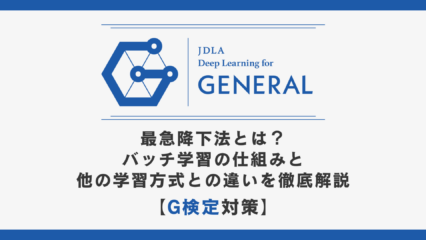 G検定対策
G検定対策 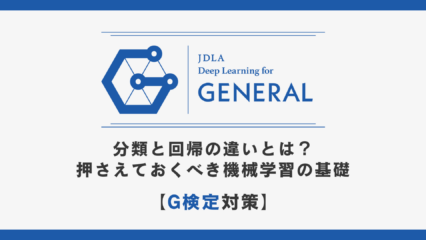 G検定対策
G検定対策 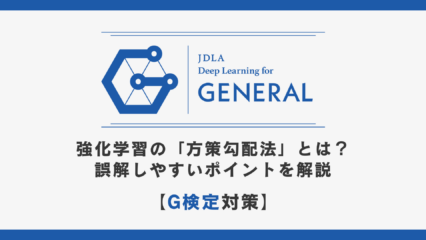 G検定対策
G検定対策 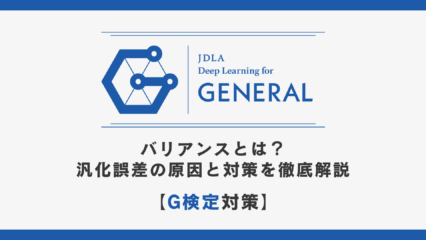 G検定対策
G検定対策 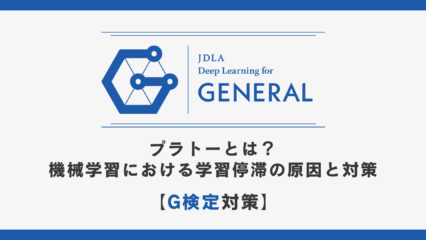 G検定対策
G検定対策 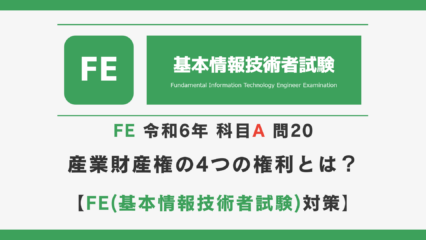 FE対策
FE対策  G検定対策
G検定対策 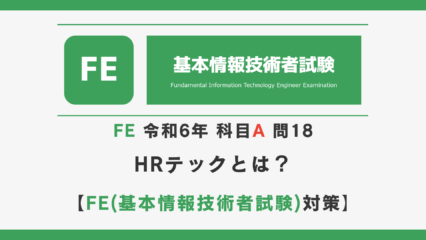 FE対策
FE対策 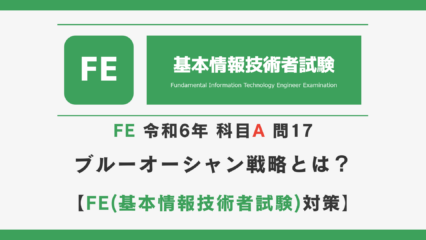 FE対策
FE対策 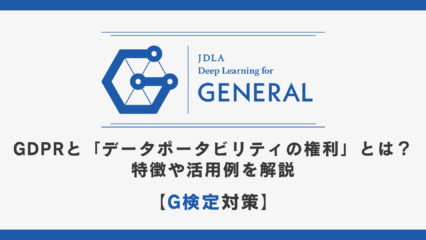 G検定対策
G検定対策 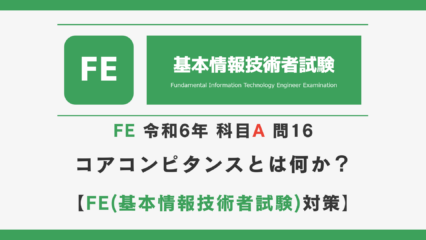 FE対策
FE対策 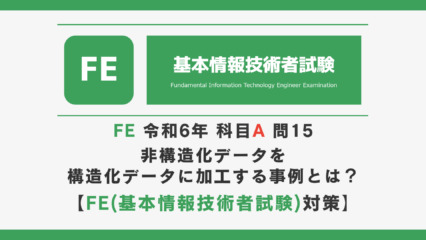 FE対策
FE対策  プログラミング
プログラミング 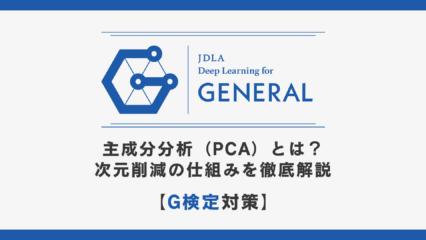 G検定対策
G検定対策 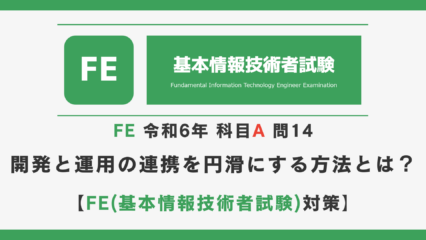 FE対策
FE対策 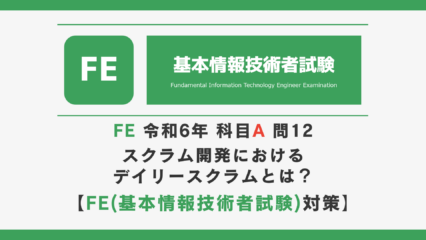 FE対策
FE対策  G検定対策
G検定対策 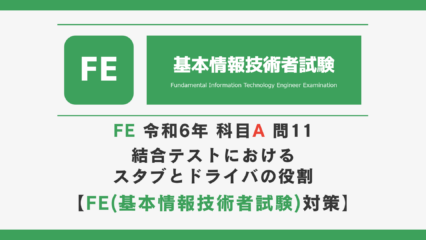 FE対策
FE対策 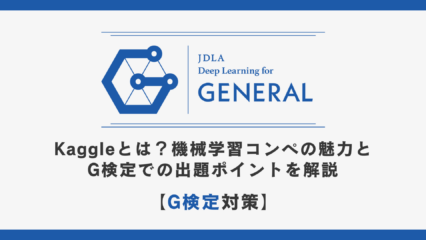 G検定対策
G検定対策 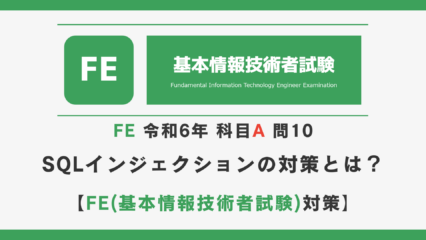 FE対策
FE対策 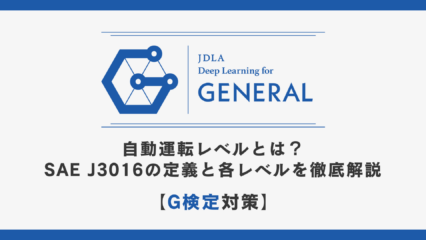 G検定対策
G検定対策