はじめに
G検定では、機械学習の基本的な手法から深層学習の応用まで、幅広い知識が求められる。その中でも「アンサンブル学習」は、高得点を狙ううえで避けて通れない重要なトピックのひとつだ。
今回は実際に出題された過去問を題材に、「アンサンブル法の基本」と「なぜその選択肢が不適切なのか」を明確に解説していく。しっかりと理解を深めておこう。
アンサンブル学習とは何か?
アンサンブル学習とは、複数の学習器(モデル)を組み合わせることで、1つの高性能な予測モデルを構築する手法だ。単独のモデルでは捉えきれないパターンも、複数モデルの組み合わせによって精度を向上させることが期待される。
代表的なアンサンブル法には次のような種類が存在する:
- バギング(Bagging)
→ 同じ学習アルゴリズムを異なるデータセットで学習させ、その結果を平均や多数決で統合。 -
ブースティング(Boosting)
→ 弱い学習器を順番に学習させ、誤分類されたデータに重点を置くことで強い学習器を作り出す。 -
スタッキング(Stacking)
→ 複数の異なるモデルの出力をメタモデル(第二段階のモデル)に渡して、最終的な予測を得る。
このように、アンサンブル法にはいくつかの種類があるが、G検定では「不適切な手法」を選ぶ問題も登場している。
問題:アンサンブル学習として不適切な手法を選べ
実際のG検定問題を紹介する。
学習器を組み合わせて、性能の高い学習器を作る方法であるアンサンブル法の方法として、最も不適切な選択肢を選べ。
選択肢:
- ARIMA
- スタッキング
- ブースティング
- バギング
正解は「1. ARIMA」
一見すると見慣れた選択肢が並んでいるが、よく見ると1つだけ明らかに異質な手法が紛れ込んでいる。それが「ARIMA」だ。
なぜ「ARIMA」が不適切なのか?
ARIMAとは「自己回帰和分移動平均モデル(AutoRegressive Integrated Moving Average)」の略であり、時系列データの予測に特化した統計モデルの一種である。
特徴は以下の通り:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 用途 | 時系列予測(株価、売上など) |
| モデルの型 | 統計モデル(線形モデル) |
| 学習方法 | パラメータ推定による解析的手法 |
| アンサンブルとの関連 | 基本的に存在しない |
ARIMAは、複数の学習器を組み合わせる設計思想を持たない。したがって、アンサンブル学習とは無関係の手法であると判断できる。
他の選択肢が適切な理由
| 選択肢 | 説明 | アンサンブル手法との関連性 |
|---|---|---|
| スタッキング | 複数の異なるモデルの出力を統合する手法。 | 明確なアンサンブル法の一種。 |
| ブースティング | 学習器を逐次構築して誤差を修正する。 | AdaboostやXGBoostなどで有名。 |
| バギング | データをランダムにサブセットし、複数の学習器を構築して統合。 | ランダムフォレストが代表例。 |
これらの手法は、いずれもアンサンブル学習の基本に位置づけられる。過去問対策としては、これらの名前を覚えるだけでなく、その仕組みと違いを理解しておくことが重要だ。
まとめ
アンサンブル学習に関するG検定の問題では、「どれが仲間外れか」を見抜く視点が求められる。
✅ アンサンブル法に該当するのは、「スタッキング」「ブースティング」「バギング」
✅ ARIMAは時系列予測モデルであり、アンサンブル法とは無関係
G検定では、「なぜ正解なのか」だけでなく「なぜ他の選択肢が間違っているのか」を明確に説明できるようにしておくと、応用問題にも強くなる。
このような切り口で過去問を復習することで、知識の定着と理解の深まりが期待できる。次回は他のテーマでも、同様の分析と解説を進めていこう。
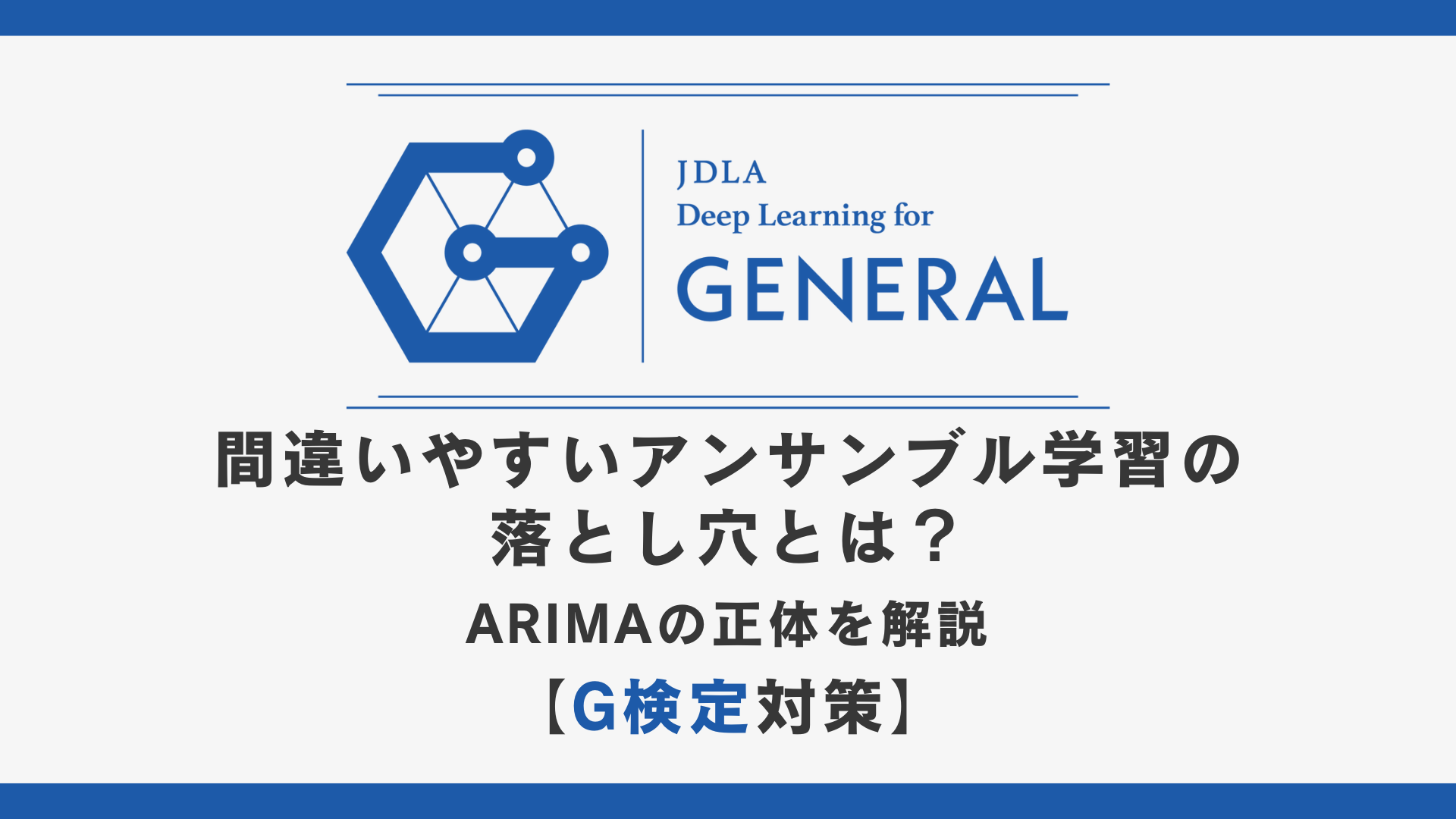
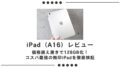

コメント