はじめに
G検定ではAI全般に関する幅広い知識が問われる。特に近年は、AIを支えるハードウェアの知識も重視されている傾向がある。
今回は「Googleが機械学習向けに開発したプロセッサはどれか?」という過去問を通じて、AI処理に用いられるプロセッサの基礎を確認しよう。
問題
機械学習に特化したGoogleの自社開発プロセッサとして、最も適切な選択肢を選べ。
選択肢
- TPU
- CUDA
- MN-Core
- Itanium
正解は「1. TPU」
なぜ「TPU」が正解なのか?
TPU(Tensor Processing Unit)は、Googleが機械学習、とりわけディープラーニング処理の高速化を目的に開発した専用プロセッサである。
2016年に発表されて以降、Googleのクラウドサービスや社内システム(例:Google 翻訳、画像認識、音声処理など)に幅広く活用されている。
TPUの特徴
- ニューラルネットワーク計算に特化したアーキテクチャ
- 高い並列処理性能
- Google Cloud Platform上で利用可能(TPUv2〜v4など進化中)
- TensorFlowとの親和性が高い
ディープラーニングにおける行列演算や畳み込み処理を高速に処理するため、GPUよりも特定用途で圧倒的な性能を発揮する。
他の選択肢が不正解な理由
CUDA
CUDA(Compute Unified Device Architecture)は、NVIDIAが開発したGPUプログラミングのフレームワークである。
プロセッサ自体の名称ではなく、「GPU上で並列処理を行うためのソフトウェア層」に該当する。
つまり、CUDAはハードウェアではないため、選択肢として不適切。
MN-Core
MN-Coreは、富士通が開発したAI専用プロセッサで、スーパーコンピュータ「富岳」やAI処理向けサーバーで使用されている。
日本製の高性能チップであり、主に国内の商用・研究向けに展開されている点が特徴。
ただし、これはGoogle製ではなく富士通製なので、出題の条件に合致しない。
Itanium
Itaniumは、IntelとHPが共同開発したサーバー向けの汎用プロセッサ。
かつてはエンタープライズ向けシステムで使用されたが、現在は主流ではなく、AI向けの設計でもない。
TPUのようにAI処理に特化したハードウェアとは明確に異なる。
TPUが活用される具体例
実務でもTPUは多くの現場で利用されている。代表的なケースを紹介しよう。
1. Google翻訳
言語翻訳モデルを高速かつ低遅延で動作させるために、TPUがバックエンドで稼働している。
2. 自動運転分野
リアルタイムでの画像認識処理を行うため、オンデバイスまたはクラウド経由でTPUが活用されるケースが増えている。
3. 研究機関での大規模モデル学習
TPU Podsと呼ばれるクラスタを使えば、数百ノードの分散学習も可能。ChatGPTのような巨大モデルのトレーニングにも利用可能だ。
まとめ
G検定では、単に「用語を暗記する」のではなく、なぜその選択肢が正しいのか/誤っているのかを理解することが重要となる。
今回の問題を振り返ると、次のように整理できる:
✅ 正解:「TPU」=Googleが開発した、AI専用プロセッサ
❌ CUDA:GPUプログラミング用のソフトウェア技術
❌ MN-Core:富士通製のプロセッサでGoogle製ではない
❌ Itanium:AI用途ではなく、旧式のサーバー向け汎用CPU
G検定を受けるなら、AI技術とその周辺ハードウェアの関係性にも注目し、知識を体系的に整理しておくことが合格への近道だ。
今後も過去問を通じて、AI技術の本質を読み解いていこう。
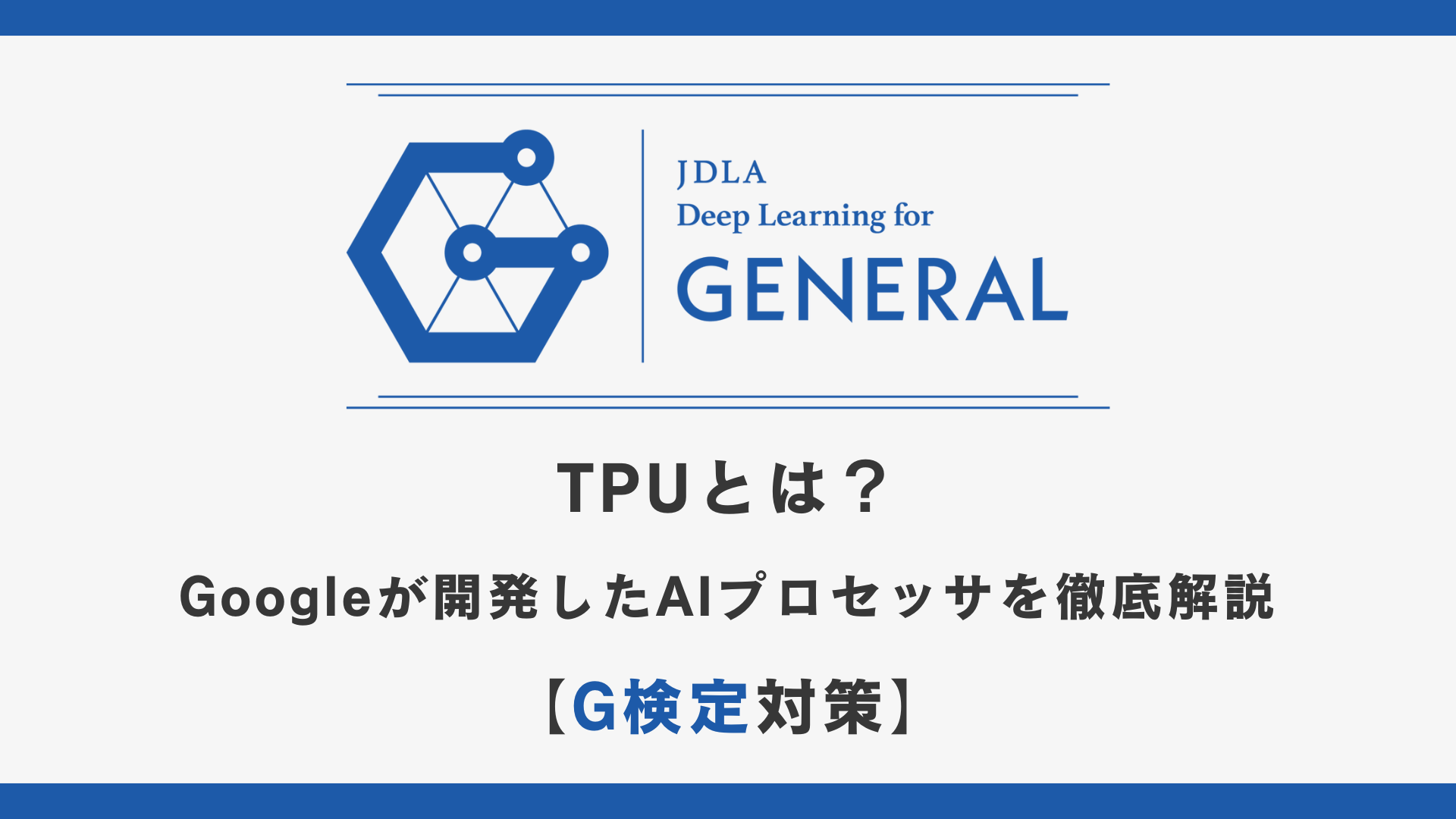


コメント