はじめに
G検定では人工知能(AI)の基礎から応用まで、幅広い知識が問われる。中でも自然言語処理(NLP)は毎年のように出題される重要分野だ。
今回扱うのは、「第2次AIブーム」期における自然言語処理の知識表現に関する問題。選択肢に並ぶ技術用語を正確に理解することで、応用力を養える内容となっている。
G検定の本試験に備え、過去問をもとに重要ポイントを解説する。
過去問の紹介
まずは実際の出題文を確認しよう。
第2次AIブームでは、いかにして機械に知識を与えるかがテーマであった。
自然言語処理の研究では、文や単語の意味、概念間の連想関係、知識などを図式化し定義する(●)が提案された。
選択肢
- 意味ネットワーク
- ベクトル空間モデル
- AIシステム
- サイキット・ラーン
正解は「1. 意味ネットワーク」
意味ネットワークとは何か?
意味ネットワーク(Semantic Network)は、単語や概念同士の関係性を図式化して表現するための手法だ。
例えば「犬 → 動物 → 生物」といった階層関係や、「犬 → 吠える」「猫 → 鳴く」のような動作属性など、概念のつながりをノードとエッジで表現する。
これは第2次AIブーム(1980年代)に盛んだった知識表現技術の代表格の一つであり、「機械にどうやって人間の知識を教えるか?」という問いに対する試みだった。
他の選択肢との違いは?
正解以外の選択肢も、一見それらしく見えるが、文脈上では適合しない。それぞれの特徴を見ていこう。
| 選択肢 | 説明 | なぜ不正解か |
|---|---|---|
| ベクトル空間モデル | 単語や文章を数値ベクトルとして表現するモデル。主に情報検索や分散表現で使われる。 | 文や単語の「意味」や「連想関係」を図式化するものではない。数値化された空間上で距離や類似度を見る手法であり、知識表現の意図とは異なる。 |
| AIシステム | AIを活用したシステム全般を指す抽象的な言葉。 | 「提案された技術」としてはあまりに広すぎ、具体的な方法論ではない。文脈的にも不明確。 |
| サイキット・ラーン | Pythonの機械学習ライブラリ。分類・回帰・クラスタリングなど多用途。 | 自然言語処理や知識表現を主目的とするものではなく、歴史的背景とも無関係。選択肢として場違い。 |
このように、意味ネットワークのみが「知識を図式化・定義する」点で文脈に合致している。
なぜこの問題が重要か?
第2次AIブームを理解することは、現代のAI技術と比較する上でも重要だ。
当時の研究は、「知識をいかにして機械に明示的に与えるか?」に焦点が当たっていた。一方で、現在のAI(第3次AIブーム)では、ビッグデータを通じて「機械が自ら学習する」方向にシフトしている。
意味ネットワークは、AIに人間の知識をそのまま教え込む発想を象徴する手法であり、現在のニューラルネットワークや深層学習とはアプローチが根本的に異なる。
学習のポイントと実務的な視点
G検定対策としては、以下のポイントを押さえるとよい。
- 意味ネットワークの特徴:概念間の連想関係を明示的に図で示す
- ベクトル空間モデルとの違い:数値的な距離と意味的な関係性は別物
- 時代背景との結びつけ:第2次AIブームでは記号処理や知識表現が中心
また、現場で自然言語処理を扱うエンジニアにとっても、「意味ネットワークのような知識表現は、対話AIやエキスパートシステムで今なお使われる」という事実を知っておくことは重要だ。
まとめ
G検定における自然言語処理の出題は、単なる技術用語の暗記では太刀打ちできない。
文脈と歴史背景を読み取り、「なぜその技術が生まれたのか?」を理解することで、本質的な力が身につく。
✅ 意味ネットワークは、概念間の関係を視覚的に表現する知識表現手法
✅ 第2次AIブームでは、明示的な知識の構造化が主なテーマだった
✅ 他の選択肢との違いを正確に説明できることが合格への近道
G検定の学習を進めるうえで、このような過去問を活用し、深い理解につなげていこう。次回は「ベクトル空間モデル」や「Word2Vec」についても掘り下げていく予定だ。
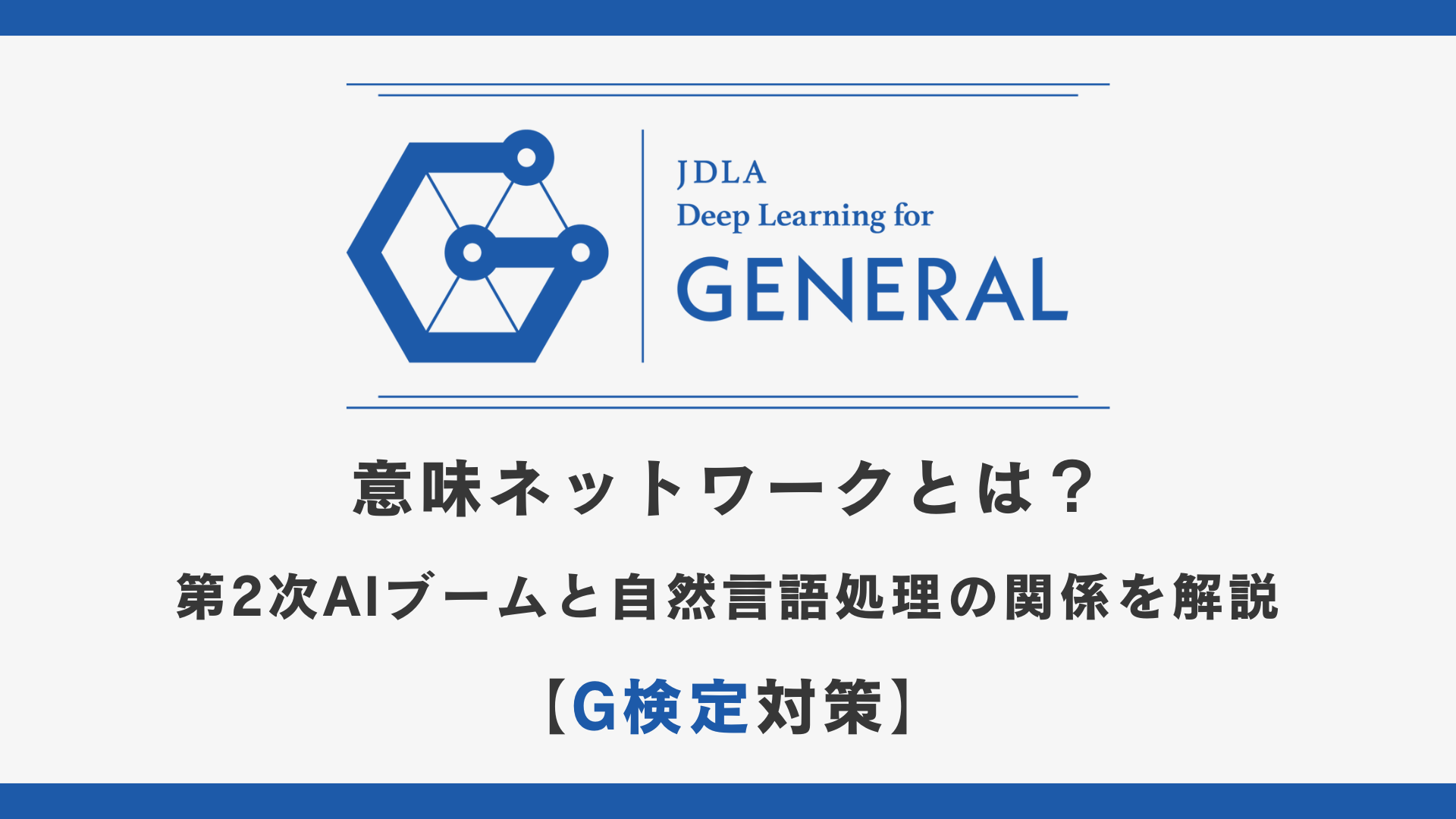


コメント