はじめに
G検定(ジェネラリスト検定)は、人工知能に関する幅広い知識を問う資格試験であり、出題範囲はAIの基礎理論から社会的影響まで多岐にわたる。その中でも、「シンギュラリティ(技術的特異点)」という言葉は、しばしば登場する重要なキーワードだ。
今回は、G検定の過去問をひもときながら、「シンギュラリティ」が問われる背景や選択肢の違いについて整理する。単なる暗記ではなく、周辺知識を交えて深く理解しておきたい。
過去問をチェック
まずは実際に出題された問題を見てみよう。
以下の文章を読み、(●)に最もよく当てはまる選択肢を選べ。
(●)は、レイ・カーツワイルが提唱した、「\$1,000で手に入るコンピュータの性能が全人類の脳の計算性能を上回る時点」のことであり、そこから、「人工知能などの技術が、自ら人間より賢い知能を生み出す事が可能になる時点」という意味で広まった。
選択肢
- ユビキタス
- シンギュラリティ
- クラウドコンピューティング
- 第3次AIブーム
正解は「2. シンギュラリティ」
なぜ「シンギュラリティ」が正解なのか?
問題文に出てくるレイ・カーツワイルは、未来学者として知られ、技術的特異点(テクノロジカル・シンギュラリティ)という概念を広めた人物だ。彼の主張によると、AIが人間の知能を超える転換点が必ず訪れるとされている。
この転換点では、AIが自らより優れたAIを生み出し、その結果、爆発的な技術進化が起こる。まさにこの考えこそが「シンギュラリティ」と呼ばれるものである。
他の選択肢が誤りである理由
正解を選ぶだけでなく、「なぜ他の選択肢は不正解なのか?」という視点もG検定の学習では重要になる。各選択肢の意味を確認してみよう。
| 選択肢 | 内容 | 本問との関連性 |
|---|---|---|
| ユビキタス | 「いつでも・どこでも・誰でも」情報にアクセスできる技術概念 | ネットワーク化の発展に関する概念であり、AIの進化点とは無関係 |
| クラウドコンピューティング | インターネット上のサーバーを活用してデータ処理を行う技術 | コンピュータ性能向上には関係あるが、「知能が知能を超える」という観点ではない |
| 第3次AIブーム | ディープラーニング技術の発展によるAIブーム(2010年代〜) | 時代背景として重要ではあるが、シンギュラリティそのものではない |
シンギュラリティの背景と応用
1. レイ・カーツワイルの予測
彼は「2045年にシンギュラリティが訪れる」と予測している。その根拠として、コンピュータの性能が指数関数的に成長していることを挙げている。ムーアの法則に代表される技術進化のスピードを根拠に、「いつかAIは人間を超える」と断言しているのだ。
2. シンギュラリティの意味する未来
この概念が示唆する未来は楽観的なものばかりではない。技術の進化が人間の制御を超えるリスクも含んでいる。そのため、倫理や法律の整備が求められており、G検定でも「AI倫理」「社会的インパクト」に関連した問題として頻出する。
試験対策として押さえるポイント
G検定では、以下のような観点で「シンギュラリティ」が問われる可能性がある。
- レイ・カーツワイルの名前とその提唱内容
- シンギュラリティが意味する技術的な転換点の定義
- 他の技術概念(ユビキタス、クラウド、第3次AIブーム)との違い
- 社会的・倫理的な観点からの影響とリスク
単語だけでなく、その背後にある「背景」や「つながり」を理解することが、得点力を高めるコツである。
まとめ
今回の過去問では、「シンギュラリティ」という技術的特異点の概念が問われた。これは単なる知識ではなく、AIの未来をどう考えるかという本質的な問題でもある。
✅ レイ・カーツワイルの提唱する技術的特異点=シンギュラリティ
✅ 単なる技術進化ではなく、AIが自律的に進化を加速させる点がカギ
✅ ユビキタスやクラウドなど他の用語との違いを明確に理解する
G検定では、このように選択肢の意味や背景まで含めた理解が求められる。単なる暗記ではなく、実社会での応用や倫理的課題にも目を向けながら、確かな知識を積み上げていこう。
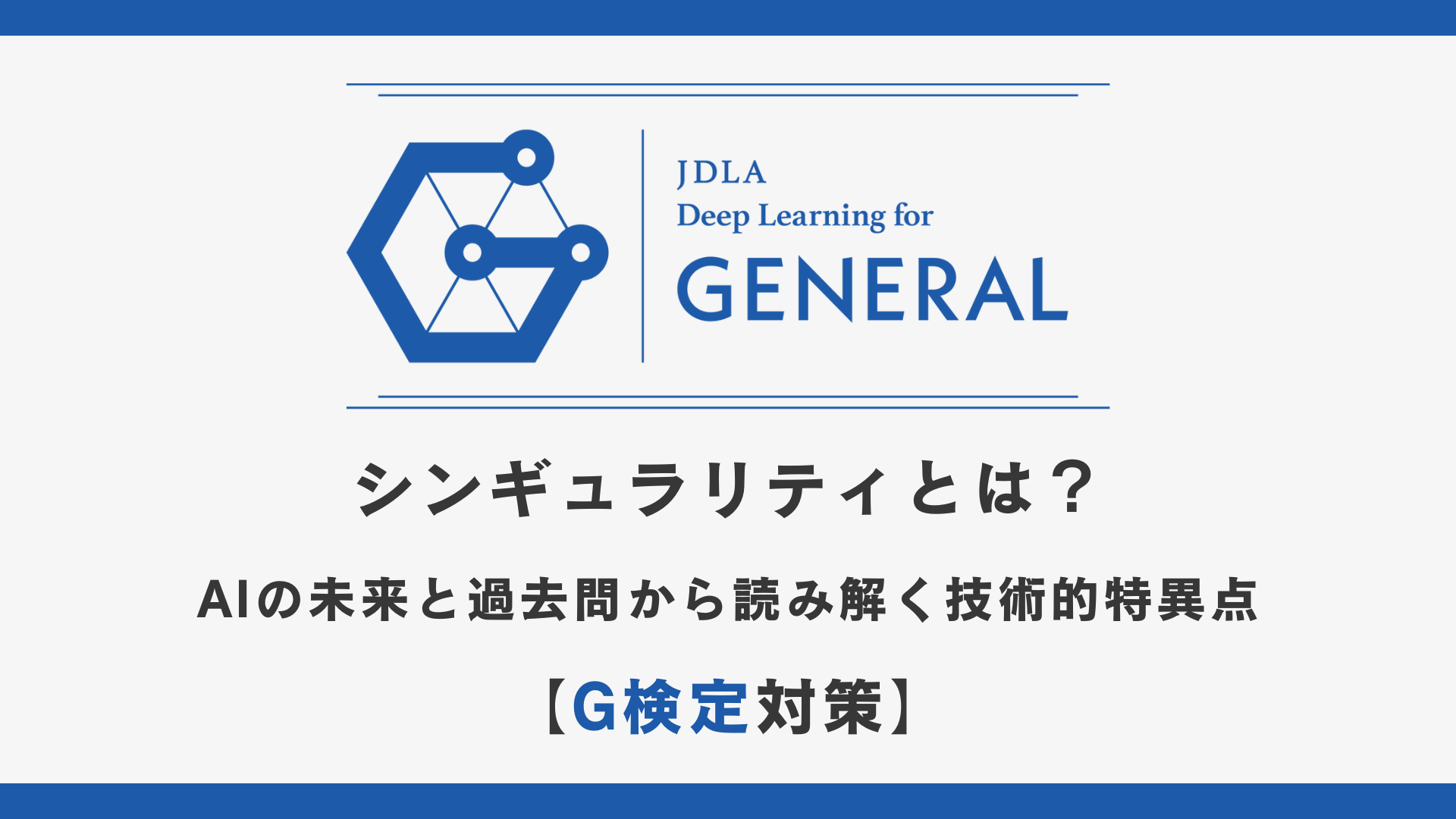

コメント