はじめに
自動運転技術の進歩は、私たちの社会に大きな変化をもたらしている。特に、自動運転中のドライバーの役割に関する法律の整備が進んでいる点は見逃せない。
2019年5月の道路交通法改正では、「条件付きで認められる行為」が明確に定められたが、どのような行為が許可されるようになったのか?
G検定で問われた問題を通じて、法改正のポイントを整理していこう。
2019年5月の道路交通法改正で認められた行為とは?
G検定の過去問を見てみよう。
2019年5月の道路交通法の改正によって、自動運転中に条件付きで認められるようになったこととして、最も適切な選択肢を選べ。
選択肢
- 睡眠
- 運転席の無人
- アルコールの摂取
- スマートフォンや携帯電話を手に持っての操作
正解は「4. スマートフォンや携帯電話を手に持っての操作」
では、なぜこの選択肢が正解なのか?他の選択肢はなぜ誤りなのか?詳しく解説していこう。
道路交通法改正のポイント
2019年の道路交通法改正により、日本では自動運転レベル3の車両に関する規定が明確になった。
自動運転レベル3では、特定の条件下(例えば高速道路走行時)においてシステムが運転を担当し、ドライバーは運転操作から解放される。
その結果、「一定の条件下でスマートフォンなどの操作が認められる」 という大きな変更が加えられた。
ただし、完全に自由になるわけではなく、システムが介入を求めた際には即座に運転を再開できる状態である必要がある。
このため、スマートフォンを使用できる時間や状況は厳しく制限されている。
なぜ他の選択肢は誤りなのか?
G検定の試験対策では、「正解を知るだけでなく、他の選択肢がなぜ間違いなのかを理解すること」が重要だ。
では、他の選択肢がなぜ誤りなのかを見ていこう。
1. 睡眠
- 自動運転レベル3では、システムが運転を担当するとはいえ、ドライバーは緊急時に操作を引き継ぐ必要がある。
- そのため、睡眠は禁止されている。
- 仮に運転中にドライバーが眠ってしまった場合、法的に問題となるだけでなく、安全性の面でも非常に危険だ。
2. 運転席の無人
- 自動運転レベル4以上になれば、一定の条件下で完全無人運転が可能となるが、2019年の道路交通法改正ではレベル3の運用が主な対象となっている。
- レベル3ではドライバーが車内にいることが必須であり、無人運転は認められていない。
3. アルコールの摂取
- 日本の道路交通法では、運転者が飲酒してはいけないというルールは自動運転車であっても適用される。
- レベル3では、万が一システムが介入を求めた際にドライバーが運転を引き継がなければならないため、飲酒は禁止されている。
- 将来的にレベル4やレベル5の完全自動運転が実現すれば、アルコール摂取が許可される可能性はあるが、現状ではまだ先の話だ。
自動運転レベル別の運転者の役割
自動運転技術はレベル0~レベル5に分類され、それぞれで運転者の役割が異なる。
今回の法改正は主にレベル3に関するものだったため、他のレベルと比較しながら理解を深めておこう。
| 自動運転レベル | 運転者の役割 | スマホ操作 | 睡眠 | 無人運転 | 飲酒 |
|---|---|---|---|---|---|
| レベル0(手動運転) | すべての操作をドライバーが実施 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| レベル1(運転支援) | アシスト機能あり、基本的に運転はドライバー | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| レベル2(部分自動運転) | 一定条件下でハンドル・アクセル操作を支援 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| レベル3(条件付き自動運転) | 特定条件下で自動運転、ドライバーは待機 | ⭕(条件付き) | ❌ | ❌ | ❌ |
| レベル4(高度自動運転) | 一部環境で無人運転可能 | ⭕ | ⭕(特定条件下) | ⭕ | ❌ |
| レベル5(完全自動運転) | すべての環境で完全自動運転 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
この表からもわかるように、2019年の改正で対象となったレベル3では「スマートフォンの操作」が唯一条件付きで認められるが、それ以外の行為はまだ認められていない。
まとめ
2019年5月の道路交通法改正は、自動運転レベル3の実用化を前提とした規制緩和であった。
その中で、一定の条件下でスマートフォンの操作が認められるようになったことは、G検定でも重要な知識となる。
試験対策ポイントを整理すると:
✔ スマートフォン操作が条件付きで解禁された(ただし運転の引き継ぎは必須)
✔ 睡眠・無人運転・飲酒は依然として禁止
✔ 自動運転レベル3の範囲を正しく理解することが重要
G検定では、このような最新の技術動向や法律の変化も問われるため、試験勉強の際は技術だけでなく法改正にも注目することが大切だ。
将来的にレベル4やレベル5が普及すれば、法律のさらなる改正が行われる可能性が高い。
こうした変化をキャッチアップしながら、AI技術の進展を理解していこう。
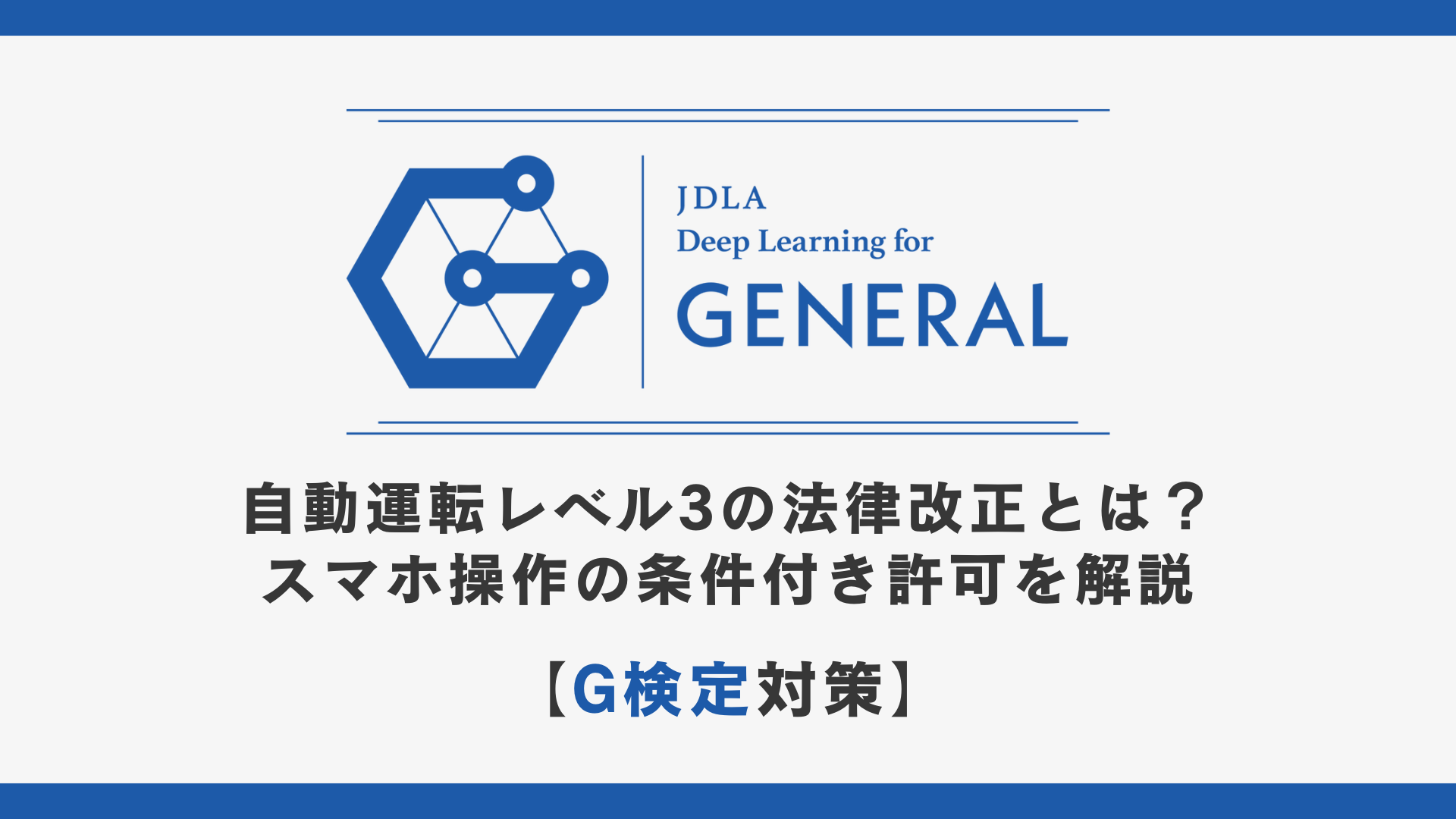


コメント