はじめに
G検定では、ディープラーニングの応用手法や周辺技術に関する出題が多く見られる。
中でも「次元削減」に関する問題は、画像処理やデータ可視化など様々な場面で活用されるため、必ず押さえておきたいトピックだ。
今回はG検定の過去問を取り上げ、「t-SNE(t-distributed Stochastic Neighbor Embedding)」に関する基礎知識と、その特徴について整理していく。
問題:t-SNEの「t」の意味を表す、最も適切な選択肢はどれか?
SNEを改良したアルゴリズムであるt-SNEのtの意味を表している、最も適切な選択肢を選べ。
選択肢
- Translation
- Transformer
- t分布
- Text
正解は「3. t分布」
t-SNEとは何か?
t-SNEは、次元削減の手法の一つであり、高次元のデータを2次元や3次元などに落とし込んで視覚的に理解しやすくする技術。
SNE(Stochastic Neighbor Embedding)という既存手法を改良したものであり、高次元空間の局所的なデータ構造を低次元空間でも保つ点が特徴だ。
「t」の正体:t分布
アルゴリズム名の「t」は、「t分布(Student’s t-distribution)」を指している。
SNEでは高次元空間と低次元空間の類似度の計算にガウス分布を用いるが、t-SNEでは低次元空間における類似度の表現にt分布を採用している。
なぜt分布を使うのか?
ガウス分布に比べて、t分布は裾野が広いため、データ点が密集している部分と孤立している部分の違いがより強調されやすい。
これにより、データのクラスタ構造が可視化しやすくなるというメリットがある。
なぜ他の選択肢ではないのか?
| 選択肢 | 解説 |
|---|---|
| Translation | 翻訳を意味するが、t-SNEとは無関係。次元削減とも関係がない。 |
| Transformer | 自然言語処理で用いられるモデルの名称。t-SNEとは別の分野の技術。 |
| Text | 一般的な単語だが、t-SNEのアルゴリズム名とは無関係。 |
t-SNEの活用例
t-SNEは主に以下のような場面で用いられる。
1. 画像分類モデルの特徴量可視化
CNNなどの画像分類モデルから得られる高次元の特徴量を2次元に可視化し、クラス間の分布を直感的に確認するために使われる。
2. 教師なし学習後のクラスタ分析
ラベルのないデータでも、t-SNEを使えば似たデータ同士のグルーピングが見える化できる。K-meansなどのクラスタリングと併用されることも多い。
3. アノマリー検出
高次元データにおける外れ値(異常)を視覚的に見つけやすくするためにt-SNEを活用するケースもある。
t-SNEの実装(Python例)
Pythonでは、scikit-learnのTSNEクラスを使うことで簡単にt-SNEを実行できる。
from sklearn.manifold import TSNE
import matplotlib.pyplot as plt
# 仮の高次元データ(例:手書き数字データなど)
X_high = ... # 高次元データ
y = ... # ラベル情報
# t-SNEによる次元削減
tsne = TSNE(n_components=2, random_state=0)
X_low = tsne.fit_transform(X_high)
# プロット表示
plt.scatter(X_low[:, 0], X_low[:, 1], c=y)
plt.title("t-SNEによる次元削減可視化")
plt.show()
このように、データのクラスタ傾向を一目で把握できるようになる。
まとめ
G検定では、「t-SNE」などの次元削減手法に関する問題が出題される。
名称の意味や使われている数理的背景(t分布)を理解しておくことが、確実な得点につながる。
✅ t-SNEとは? → 高次元データを低次元に可視化する手法
✅ 「t」の意味 → ガウス分布ではなくt分布を用いることから命名
✅ 実務応用 → 画像分類、クラスタリング、異常検出など幅広く活用可能
次元削減の意義を理解したうえで、他の手法(PCAやUMAPなど)との違いにも目を向けておくと、さらに理解が深まるだろう。
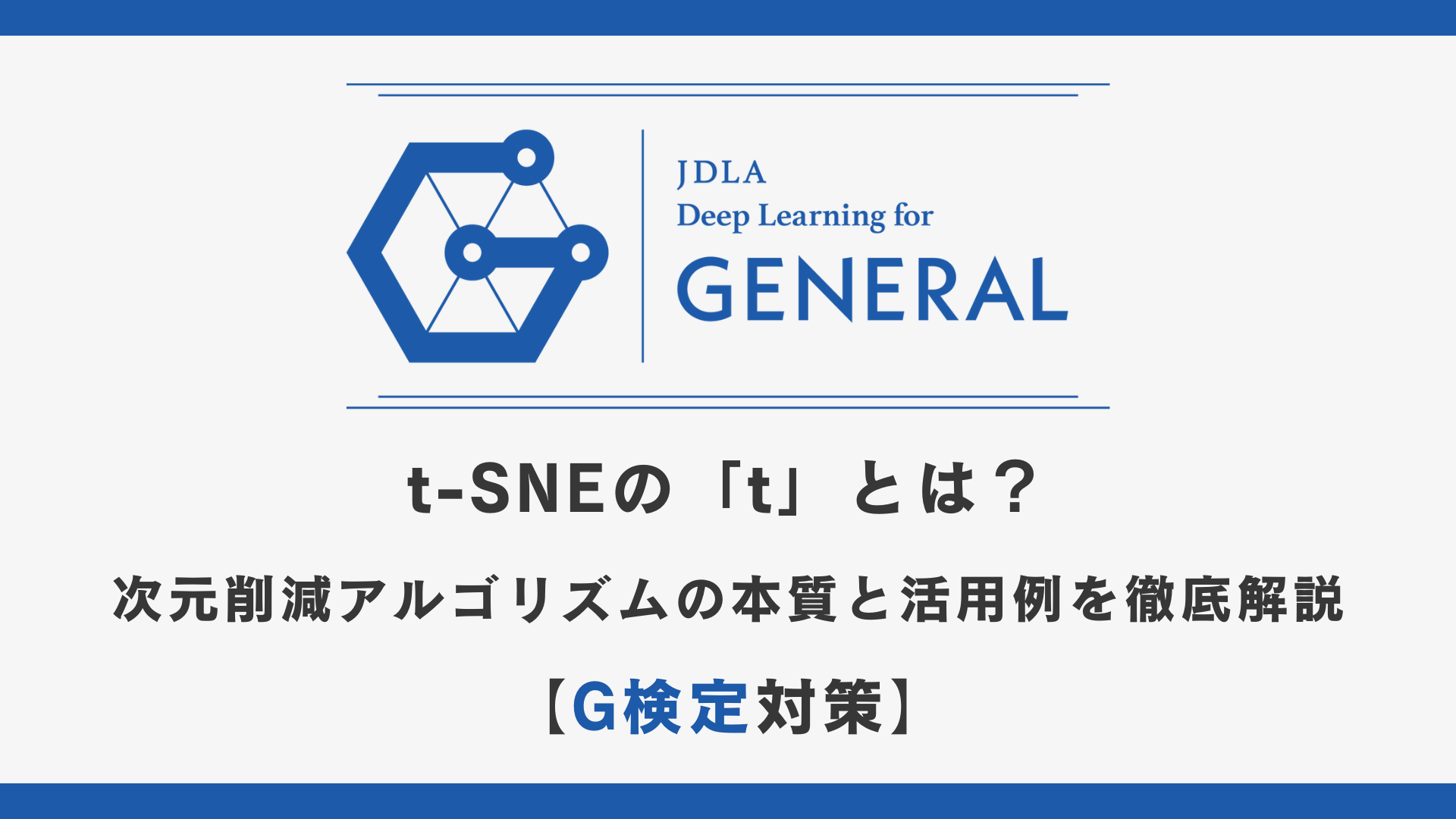


コメント