はじめに
G検定では、機械学習や統計学の基本概念についての知識が幅広く問われる。
その中でも「主成分分析(PCA)」は、次元削減の代表的な手法として頻出する重要トピックだ。
今回は、G検定の過去問を題材にしながら、「主成分分析とは何か?」を明確にし、類似しやすい選択肢との違いを整理していく。曖昧な理解を解消し、確実な知識に変えていこう。
問題:主成分分析の手法の説明として、最も適切な選択肢を選べ。
選択肢
- マージンの最大化を行う手法
- 相関の少ない変数に着目し、次元削減を行う手法
- クラスタの重心に一番近い点を採用する手法
- 弱学習器を並列に学習させて組み合わせる手法
正解は「2. 相関の少ない変数に着目し、次元削減を行う手法」
主成分分析(PCA:Principal Component Analysis)は、多次元データをより少ない次元に圧縮し、データの構造を効率よく表現するための技術。
ポイントは、「相関のある変数をまとめて、情報の重複を削減する」ことにある。
具体的には、元の変数同士の分散共分散行列を使い、新たな軸(主成分)を算出する。この主成分は、元の変数の情報を可能な限り保持しつつ、互いに相関がない(直交する)軸になる。
この手法により、元のデータのパターンを視覚化しやすくしたり、学習の効率を高めたりすることが可能になる。
なぜ他の選択肢は間違いなのか?
G検定の正しい理解には、「なぜ他の選択肢が誤りなのか」を明確にすることが不可欠だ。以下に各選択肢の内容とその誤りの理由を示す。
| 選択肢 | 内容 | 誤りの理由 |
|---|---|---|
| 1. マージンの最大化を行う手法 | サポートベクターマシン(SVM)の特徴 | 主成分分析は分類ではなく次元削減を目的とするため、マージン最大化とは関係ない |
| 2. 相関の少ない変数に着目し、次元削減を行う手法 | 主成分分析(PCA)の説明 | 正解 |
| 3. クラスタの重心に一番近い点を採用する手法 | K-meansクラスタリングの代表点(セントロイド)選択 | 主成分分析はクラスタ分けを行わない |
| 4. 弱学習器を並列に学習させて組み合わせる手法 | バギングやランダムフォレストなどのアンサンブル学習 | PCAは教師なし学習であり、弱学習器の概念とは無関係 |
それぞれの手法の用途や原理が異なるため、選択を誤らないよう整理しておきたい。
主成分分析の活用例
主成分分析は実務でも頻繁に登場する。特に以下のような場面でその効果を発揮する。
1. 可視化
高次元データを2次元または3次元に圧縮し、人間の目で観察可能にする。例として、顧客の購買行動を主成分でプロットすることで、傾向を直感的に把握できる。
2. ノイズ除去
高次元データの中に含まれる不要な変動(ノイズ)を削減し、本質的な構造に焦点を当てることで、モデルの性能向上につながる。
3. モデル学習の効率化
入力変数が多すぎると学習効率が落ちることがある。PCAにより次元を減らせば、学習時間の短縮や過学習の防止にも貢献する。
まとめ
G検定では、単に正解を覚えるだけでなく、「選択肢の違いを論理的に説明できるか」が重要になる。
✅ 主成分分析とは、相関のある変数を圧縮し、情報を保ちながら次元を減らす手法
✅ SVMやクラスタリング、アンサンブル学習とは目的もアルゴリズムも異なる
✅ 実務では、データの可視化やノイズ除去、学習の効率化など多様な用途がある
試験対策だけでなく、AIエンジニアとしての実務力向上にもつながるテーマなので、この機会にしっかりと理解を深めておきたい。
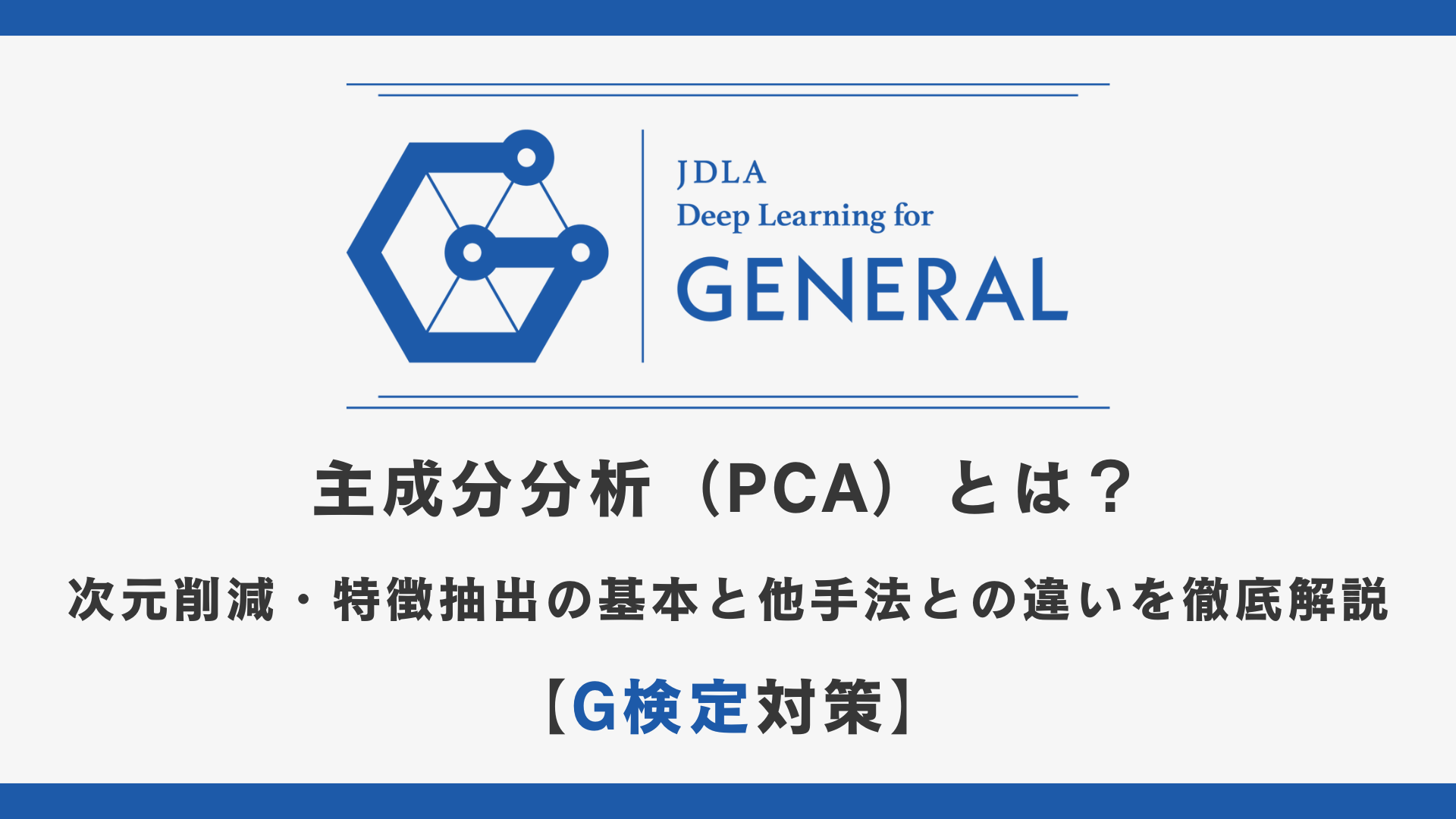


コメント