はじめに
本問では、法律の分類、賃貸借契約における義務、対抗要件、借地借家法の適用についての正しい知識が問われている。それぞれの選択肢を詳しく解説しながら、正解を導いていこう。
問題 第9問
9-1:法律の分類
9-1:問題文
法律は,様々な観点から分類することができる。法律は,法による規律を受ける者が誰であるかによって,[ア]と公法とに分類される。民法や商法のように法による規律を受ける者が私人である法律は[ア]に分類され,憲法のようにそれが国や地方公共団体である法律は公法に分類される。
また,法律をその適用対象という観点から分類すると,適用対象が限定されず一般的な法律である一般法と,対象となる事柄や人または地域などが限定されている法律である[イ]とに分類することができる。
例えば,私人間の取引一般には民法が適用されるが,その中でも特に企業などの商人間の取引には商法が適用される。この場合,民法が一般法,商法が[イ]に該当する。
さらに,法律は,[ウ]と手続法とに分類することもできる。[ウ]とは権利義務など法律関係の内容を定める法律であり,手続法とは[ウ]の内容を実現するための手続を定める法律である。
例えば,[ウ]である民法によれば,他人の過失によって損害を受けた者は,加害者に対して損害賠償請求をすることができるとされているが,被害者が民事訴訟を提起して加害者に損害賠償請求をするには,手続法である民事訴訟法の定める手続に従う必要がある。
このほか,法律の規定は,契約当事者間でこれと異なる内容の定めができるか否かという観点から,[エ]と[オ]とに分類することもできる。[エ]とは,契約当事者が法律の規定と異なる内容の取決めをしてもその効力を生じず,当事者の意思にかかわらずその適用が強制される法律の規定をいう。
これに対し,[オ]とは,契約当事者が法律の規定と異なる定めをするなど,当事者がそれに従う意思がないと認められるときは,その適用が強制されない法律の規定をいう。
ある法律の規定が[エ]か[オ]かの区別は実際には容易でないこともあるが,[エ]の中には[エ]である旨が法律上明示されているものもある。
9-1:語群
① 行政法 ② 任意法規
③ 判例法 ④ 慣習法
⑤ 不文法 ⑥ 強行法規
⑦ 取締規定 ⑧ 私法
⑨ 契約法 ⑩ 実体法
⑪ 成文法 ⑫ 自然法
⑬ 努力規定 ⑭ 社会法
⑮ 特別法
ア.私法と公法の分類
法律は,法による規律を受ける者が誰であるか によって,[ア]と公法とに分類される。
【解説】
法は、私人間の関係を規律する「私法」と、国家や地方公共団体に関する「公法」に分類される。
私法には、民法や商法が含まれる。
▶ 正解:⑧ 私法
イ.特別法
一般法と、適用対象が限定される法律である[イ]とに分類することができる。
【解説】
特定の事柄や対象に限定される法律は「特別法」と呼ばれる。
例:商法は民法の特別法。
▶ 正解:⑮ 特別法
ウ.実体法
権利義務など法律関係の内容を定める法律を[ウ]という。
【解説】
権利義務の内容を定める法律は「実体法」であり、それを実現する手続きを定める法律は「手続法」。
▶ 正解:⑩ 実体法
エ.強行法規
契約当事者が法律の規定と異なる内容の取決めをしてもその効力を生じないものを[エ]という。
【解説】
当事者の意思に関係なく適用される法律の規定は「強行法規」と呼ばれる。
例:労働基準法の最低賃金規定。
▶ 正解:⑥ 強行法規
オ.任意法規
当事者が異なる定めをするなど、当事者の意思によって適用が排除されるものを[オ]という。
【解説】
当事者の意思により異なる定めが可能な法律の規定は「任意法規」と呼ばれる。
例:売買契約の解除条件。
▶ 正解:② 任意法規
9-2:賃貸借契約
9-2:問題文
賃貸借契約においては,賃貸人は,賃借人に目的物を使用収益させる義務を負う。そのため,民法上,賃貸人は,賃借人が目的物を使用収益する上で支障がある場合には,目的物の修繕をする義務を負う。
賃貸人が行うべき修繕を賃借人が代わりに行う場合のように,目的物の保存に通常必要な費用を[ア]といい,賃借人が[ア]を支出したときには,直ちに賃貸人に対してその支出した費用の全額の償還を請求することができる。
また,賃借人が目的物に改良を加えるなど,目的物の価値を高める費用を支出した場合には,有益費として,賃貸人は,民法の規定に従い,賃貸借契約終了時に,賃借人が事実上支出した金額または目的物の価格の現存の増加額のいずれかを選択して,賃借人に償還しなければならない。賃借人は,賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において,賃貸借が終了したときは,通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに賃借物の経年変化を除き,その損傷を原状に復する義務を負う。この賃借人の義務を[イ]という。
建物の賃貸借(借家)や建物所有を目的とする土地の賃貸借(借地)については,民法の規定のほか,賃借人の保護を目的として,民法の特別法である借地借家法の適用対象となる。例えば,民法上,不動産の賃借権の対抗要件は,当該賃借権の[ウ]であるが,賃貸人は,特約がない限り,賃借権の[ウ]に協力する義務を負わないことから,賃借人が賃借権の[ウ]をすることは現実的に困難である。そこで,借地借家法上,賃借人保護の観点から,借家権と借地権について,賃借権の[ウ]以外の方法で対抗要件を備えることが認められている。
具体的には,借地借家法上,建物の賃貸借については建物の[エ]が借家権の対抗要件であり,借地については借地上の建物の[ウ]が借地権の対抗要件である。
また,民法の原則では,賃貸借期間が満了すれば,両当事者が更新に合意しない限り賃貸借契約は終了するのに対し,借地借家法の適用を受ける賃貸借契約においては,原則として,賃貸人に[オ]があると認められる場合でなければ,賃貸人の側から契約の更新を拒絶できないとされている。
9-2:語群
① 固定費 ② 登記
③ 市区町村役場への届出 ④ 帰責事由
⑤ 諾否通知義務 ⑥ 必要費
⑦ 引渡し ⑧ 契約書の作成
⑨ 減価償却費 ⑩ 仲介
⑪ 原状回復義務 ⑫ 目的物完成義務
⑬ 正当事由 ⑭ 免責事由
⑮ 供託
ア.必要費
目的物の保存に通常必要な費用を[ア]という。
【解説】
賃借人が目的物を維持するためにかかった費用を「必要費」と呼び、賃貸人に請求できる。
▶ 正解:⑥ 必要費
イ.原状回復義務
賃借物の損耗や損傷を復旧する義務を[イ]という。
【解説】
賃借人は、契約終了時に、通常の使用損耗を除き原状回復する義務がある。
▶ 正解:⑪ 原状回復義務
ウ.登記
民法上、不動産の賃借権の対抗要件は[ウ]である。
【解説】
不動産の賃借権の対抗要件は「登記」が必要(民法605条)。
借地借家法では、建物の存在が対抗要件となる。
▶ 正解:② 登記
エ.引渡し
借地借家法上、建物の[エ]が借家権の対抗要件である。
【解説】
借地借家法では、借家権を第三者に対抗するには「建物の引渡し」が必要(借地借家法31条)。
▶ 正解:⑦ 引渡し
オ.正当事由
賃貸人に[オ]があると認められる場合でなければ、賃貸人の側から契約の更新を拒絶できない。
【解説】
借地借家法では、賃貸人が更新を拒絶するには、「正当事由」が必要。
▶ 正解:⑬ 正当事由
まとめ
| 設問 | 正解 | 解説 |
|---|---|---|
| 9-1 ア | ⑧ 私法 | 私人間の関係を規律する |
| 9-1 イ | ⑮ 特別法 | 一般法の中で特定の対象に限定される |
| 9-1 ウ | ⑩ 実体法 | 権利義務の内容を定める |
| 9-1 エ | ⑥ 強行法規 | 当事者が変更できない規定 |
| 9-1 オ | ② 任意法規 | 当事者の意思で変更できる規定 |
| 9-2 ア | ⑥ 必要費 | 目的物の維持に必要な費用 |
| 9-2 イ | ⑪ 原状回復義務 | 契約終了時の修繕義務 |
| 9-2 ウ | ② 登記 | 民法上の賃借権の対抗要件 |
| 9-2 エ | ⑦ 引渡し | 借家権の対抗要件 |
| 9-2 オ | ⑬ 正当事由 | 賃貸人が更新拒絶するための要件 |
この問題では、法律の分類(私法・公法・特別法・実体法・強行法規)や、賃貸借契約の義務(必要費・原状回復義務・対抗要件・正当事由)が問われている。
特に、「強行法規と任意法規の違い」「借地借家法の保護規定」「民法と借地借家法の対抗要件の違い」を理解しておくと、試験や実務で役立つだろう。
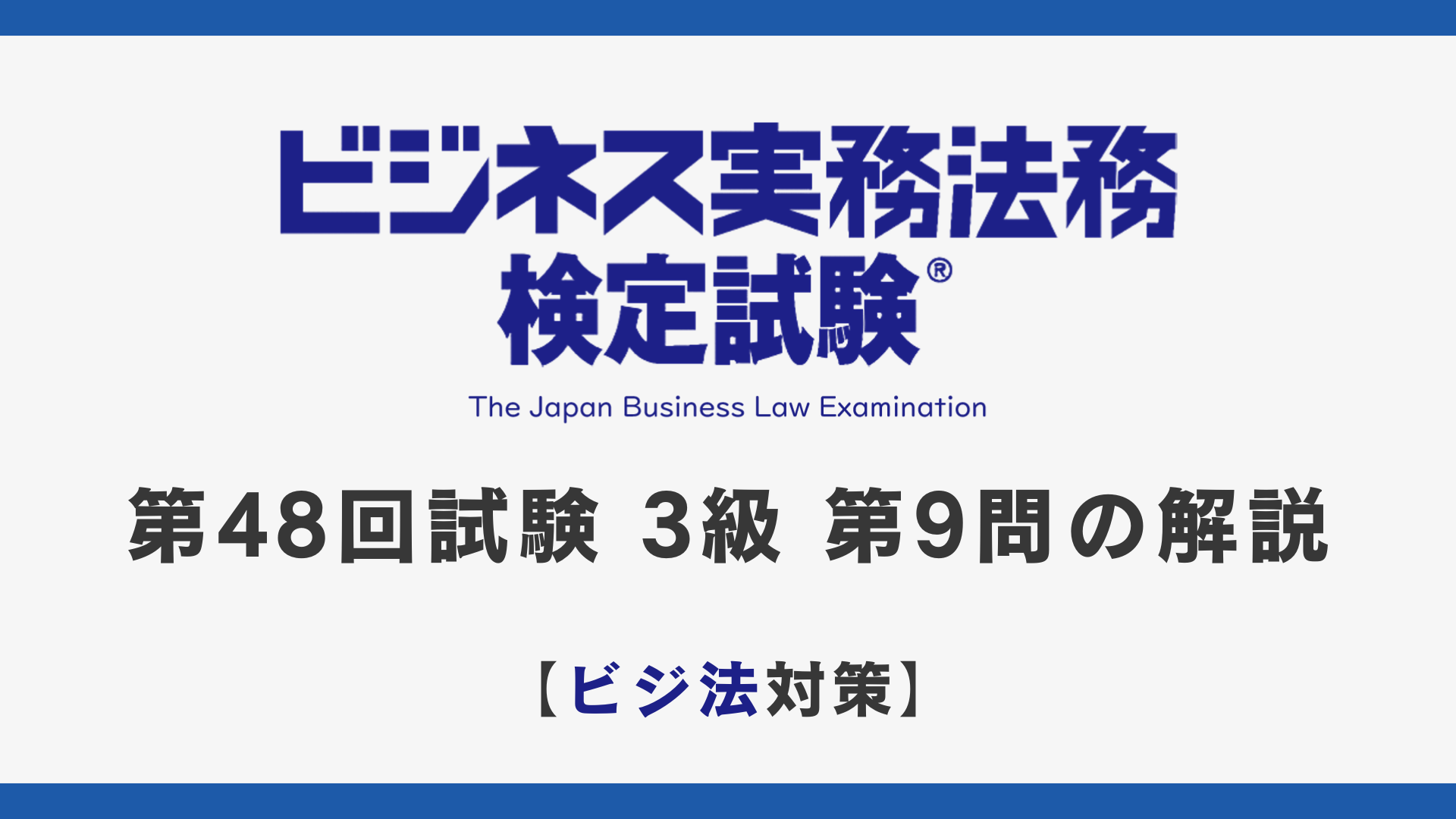


コメント