はじめに
AIの歴史を振り返ると、技術の発展はブームと冬の時代を繰り返してきた。
その中でも「第1次AIブーム」は、AIの黎明期における重要な時代だったが、ある決定的な問題によって限界を迎えた。
その問題とは何だったのか?G検定の問題を見てみよう。
「トイ・プロブレム」とは何か?
「トイ・プロブレム(Toy Problem)」は、AI研究において理論的には解けるが、実用性に乏しい単純な問題を指す。
第1次AIブーム(1950年代〜1960年代)は、
- 迷路を解く
- 簡単な数学パズルを解く
- チェスの手を探索する
といった問題を対象に研究が進められた。
しかし、これらの問題は「理想的なルールのもとで解決可能な課題」に過ぎなかった。
現実世界のように、
- 曖昧なデータ
- 未知の変数
- 大規模な計算量
を必要とする問題には対応できなかったのだ。
そのため、AIは「簡単な問題なら解けるが、現実世界の複雑な課題には適用できない」と批判され、AI研究は冬の時代を迎えることになった。
問題
実際のG検定で出題された問題を見てみる。
第1次AIブームの時代は、迷路やパズルなど限定された(●)しか解くことしかできず、現実世界に存在する複雑な問題が解けないことが課題であった。
選択肢
- 意味ネットワーク
- トイ・プロブレム
- エキスパートシステム
- A/Bテスト
正解は「2. トイ・プロブレム」
他の選択肢の誤りを解説
| 選択肢 | 解説 | 誤りの理由 |
|---|---|---|
| 意味ネットワーク | 知識をノード(概念)とエッジ(関係)で表す手法。第1次AIブームより後の技術。 | 第1次AIブームの課題ではなく、第2次AIブームの研究対象。 |
| エキスパートシステム | ルールベースで推論を行うAI。第2次AIブームで発展。 | トイ・プロブレムとは関係がない。 |
| A/Bテスト | 2つの異なる施策の比較実験手法。マーケティング分野で使用される。 | AIの限界とは無関係な概念。 |
第1次AIブームの挫折と次の展開
「トイ・プロブレム」しか解けなかった第1次AIブームは、次第に期待を失い、1970年代には「AIの冬」と呼ばれる停滞期に突入した。
しかし、この失敗が後の第2次AIブーム(エキスパートシステム)や第3次AIブーム(機械学習・ディープラーニング)の礎となったことは間違いない。
現代のAIは、トイ・プロブレムの域を超え、
- 自然言語処理(GPTモデル)
- 画像認識(ディープラーニング)
- 強化学習(AlphaGo)
など、現実世界の問題を解決する方向へと進化している。
まとめ
✅ 「トイ・プロブレム」とは、AIが理論上は解決できるが、実用性に乏しい単純な問題のこと。
✅ 第1次AIブームは、トイ・プロブレムしか解決できず、現実の問題に適用できなかったため停滞した。
✅ その後、AIの発展は第2次・第3次ブームを経て大きく進化し、現実世界の課題に対応できるようになった。
G検定では「AIの歴史」は頻出テーマの一つ。
各ブームの特徴と限界を整理しておくことで、問題を正確に解けるようになるはずだ。
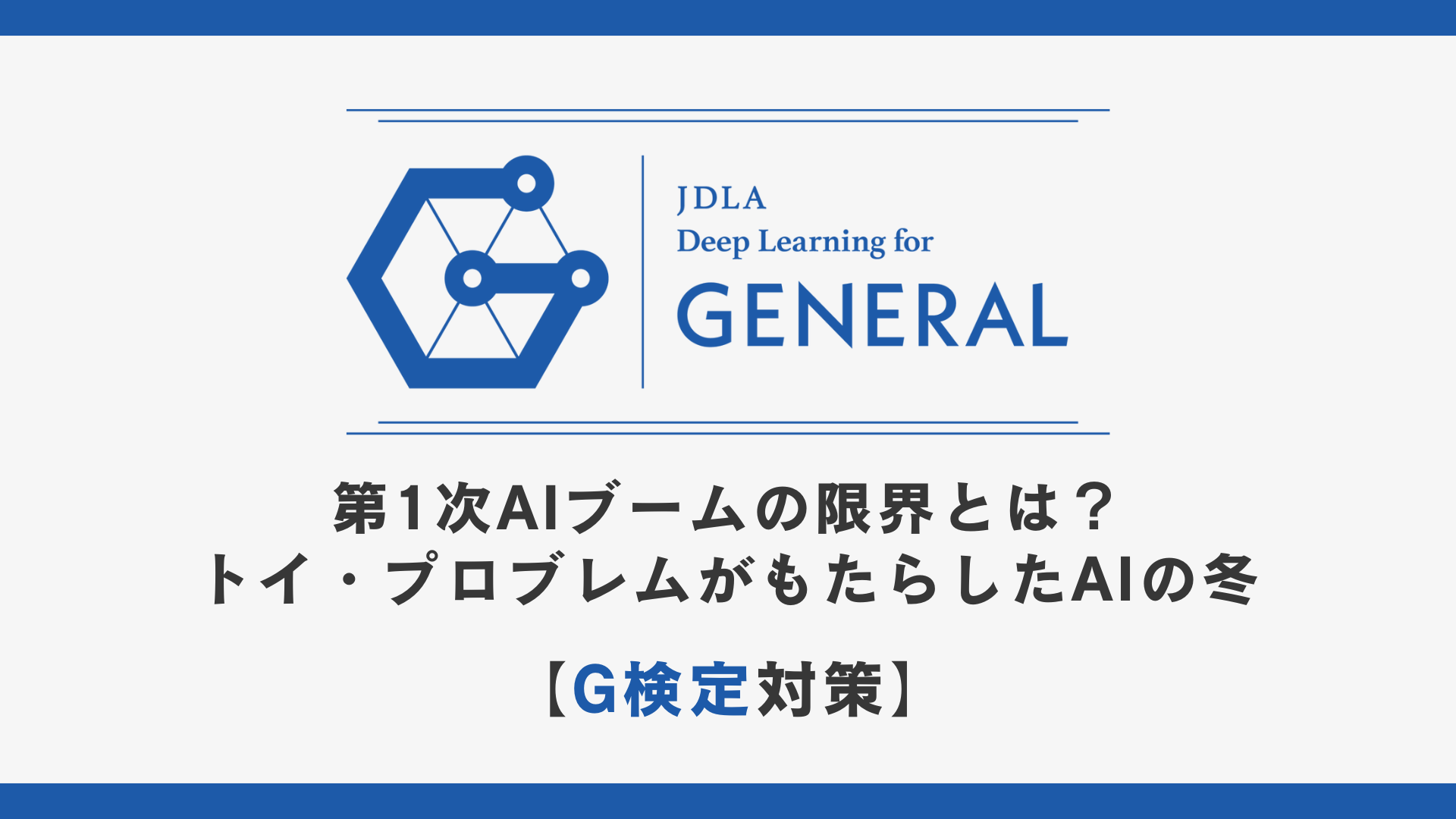


コメント