はじめに
AI開発に携わるエンジニアやプロジェクトマネージャーなら、一度は耳にする「SES契約(システムエンジニアリングサービス契約)」。
では、この契約形態がどのような法的性質を持つのか、正しく理解できているだろうか?
SES契約は「業務委託契約」の一種とされるが、具体的にはどの契約類型に該当するのか。実はここが誤解されやすいポイントだ。
本記事では、G検定の問題をもとに、SES契約の本質を解説していく。
SES契約は「準委任契約」に分類される
「準委任契約」とは?
準委任契約とは、成果物の完成を目的とせず、業務の遂行自体を委託する契約形態だ。
ポイント:
– 業務遂行が主な契約内容(成果物の完成は保証されない)
– 業務の過程に対して報酬が発生する
– 業務の進め方は原則として受託者(エンジニア側)の裁量に委ねられる
SES契約では、エンジニアが発注元のプロジェクトに参画し、一定期間業務を担当する。しかし、その業務の結果としての「成果物」については、完成義務がない。
例えば、エンジニアが開発支援としてコードを書いた場合、それが最終的にプロダクトに組み込まれるかどうかは関係ない。重要なのは「業務に従事した事実」だ。
この点が「準委任契約」の特徴であり、SES契約がこれに該当するとされる理由である。
問題
実際のG検定で出題された問題を見てみる。
民間企業でAIを開発する際に用いられる契約の1つに(●)契約があり、特にシステム開発における一部の開発を委託する場合はSES契約という。
選択肢
- 準委任
- 業務委託
- 請負
- 派遣
正解は「準委任契約」
なぜ準委任契約が適切なのか、そして他の契約形態とは何が異なるのか、詳しく見ていこう。
他の契約形態との違い
では、他の契約形態とどう違うのか?誤解を防ぐため、それぞれの契約の特徴を整理しておこう。
| 契約形態 | 特徴 | SES契約との違い |
|---|---|---|
| 業務委託 | 広義の概念であり、「準委任契約」と「請負契約」の両方を含む。 | 「業務委託契約」という表現だけではSES契約の契約類型を特定できない。 |
| 請負契約 | 成果物の完成が目的。成果が出ないと報酬は発生しない。 | SES契約では成果物完成が求められないため、不適切。 |
| 派遣契約 | 企業が労働者を派遣し、派遣先の指揮命令を受けて業務を遂行する。 | SES契約では発注者が直接指揮命令を出せないため、労働者派遣とは異なる。 |
ここで特に気をつけたいのは「請負契約」との違いだ。
請負契約の場合、発注者は「成果物の完成」を求め、それに対して報酬を支払う。
一方、SES契約(準委任契約)では、エンジニアの業務遂行そのものが契約の対象となり、完成責任は負わない。
SES契約の実務上のポイント
SES契約は、発注者側のメリットとして「柔軟な人員確保」が挙げられる。
開発プロジェクトの短期間のリソース補充や、特定のスキルを持ったエンジニアの活用が可能となる。
ただし、発注者がエンジニアに直接指示を出すことは契約上認められないため、労働者派遣契約と混同しないよう注意が必要だ。
SES契約で注意すべきポイント
- 指揮命令権の問題
- 発注者がエンジニアに直接指示すると、労働者派遣と見なされるリスクがある
- 受託側(SES事業者)を通じた業務管理が必要
- 成果物の責任範囲
- SES契約では成果物の品質保証義務がない
- 明確な納品物が必要な場合は「請負契約」にすべき
- 契約書の記載内容
- 「業務遂行」を主目的とする契約書を作成すること
- 成果物の完成義務を含めない(請負契約と混同しない)
まとめ
SES契約は「準委任契約」に分類され、成果物の完成ではなく「業務遂行」が契約の目的となる。
この契約形態を正しく理解しておかないと、請負契約や派遣契約と誤認し、契約トラブルに発展する可能性がある。
SES契約を活用する企業は多いが、正しい契約形態を認識しないまま利用すると、法的リスクが発生しかねない。
「SES=準委任契約」としっかり理解し、適切な契約運用を心がけよう。
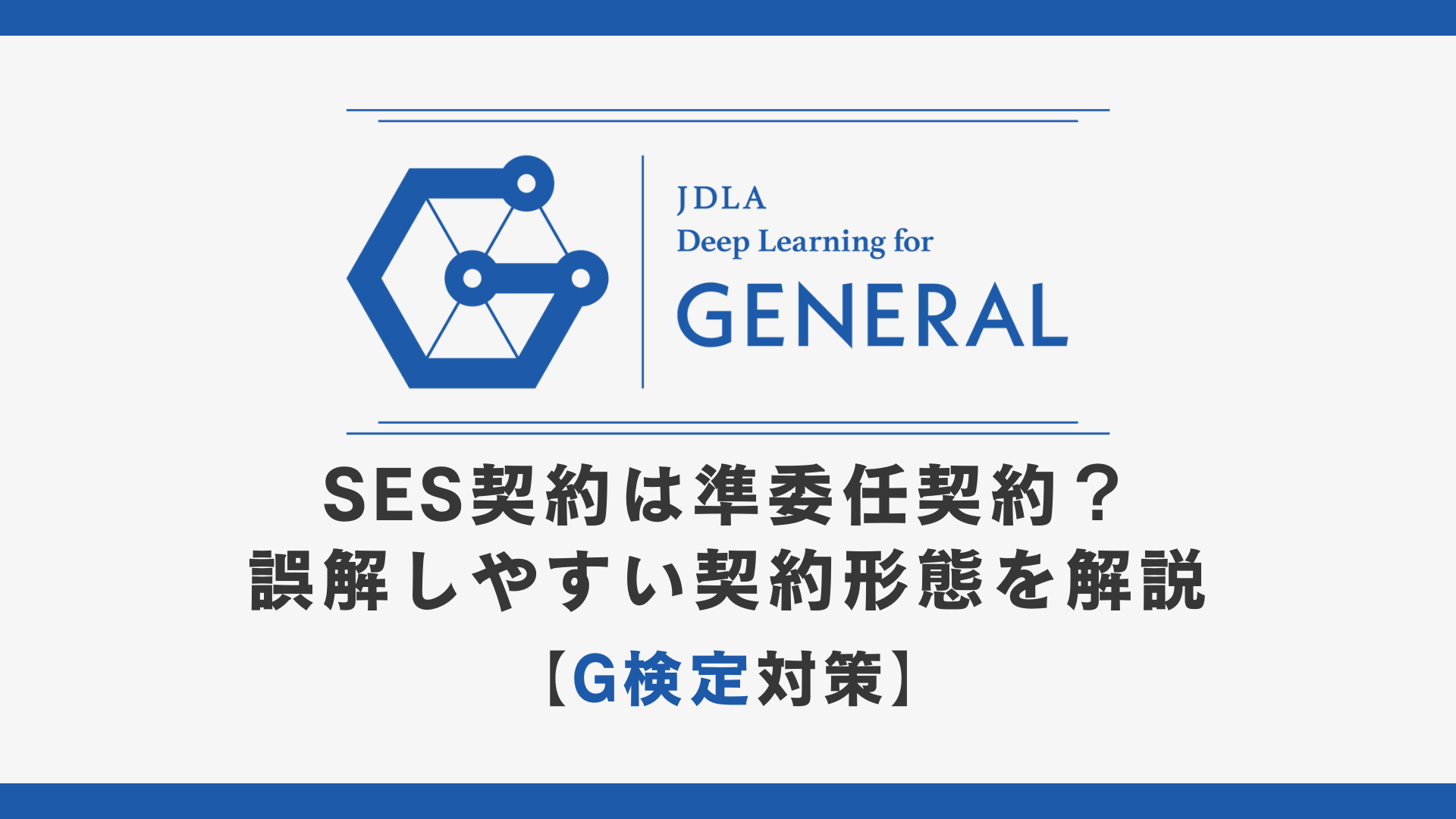


コメント