はじめに
「何があっても人を殺してはいけない」──このフレーズを、どれほど多くの人が疑いもなく信じているだろうか?
その絶対性に、ほんの少しでも揺らぎを覚えた瞬間、私たちは「倫理に反する人間」として扱われる。しかし、その言葉が常に正しく、常に公正に機能しているのかと問われれば、私は首をかしげざるを得ない。
2025年3月、ライブ配信者がファンによって刺殺されるという凄惨な事件が起きた。加害者は金銭トラブルを動機とし、被害者に対して法的な手続きもとっていたという。けれど、支払いが滞り、ついに刃が振るわれた。
この事件に対する私の感情は、単純な「殺人は絶対にダメ」では片付けられないものだった。
この記事では、倫理の「絶対性」に疑問を投げかける。そしてその裏に潜む、支配構造の正体を考察する。
正義という名の“道徳兵器”
「殺してはいけない」──一見、普遍的な倫理規範のように聞こえる。
だが、その倫理は、いつも“権力の手に握られている”とは思わないか?
歴史を振り返れば、民衆の武装解除は権力者によって巧妙に進められてきた。日本の「刀狩り」しかり、現代の銃規制しかり。表向きは「平和と安全のため」と言いながら、その実態は、「武力を持たない従順な民を作る」ための施策だったのではないか。
「どんなに搾取されても、抑圧されても、人を殺してはいけない」
この価値観が真に守っているのは誰か?
加害者か。被害者か。それとも、両者の外にいる、もっと大きな“支配の構造”か。
法が裁ききれない“人間の限界”
今回の事件では、被害者が加害者に金を借り、返済しなかったことが報じられていた。法的措置も取られていた。だが、支払い命令の後、被害者は連絡を断った。
ここで一つ問いたい。
「借金を返さなくていい社会」は、公平だろうか?
もちろん、だからといって人を殺すことが正当化されるわけではない。けれど、法が届かず、道徳も機能しない現実の中で、心の限界を迎えた人間はどうすればよかったのか。
怒りや悲しみは、法の条文には収まらない。
人は機械ではない。裏切られ、尊厳を踏みにじられれば、「もうどうでもいい」と思ってしまうことだってある。
そのとき、社会は「それでも殺してはいけない」と言う。
では聞こう。
「殺してはいけない」と叫ぶ人々は、傷ついた当事者の痛みを、どれほど想像できているのだろうか?
誰のための「絶対倫理」か?
殺人を正当化するつもりはない。ただ、「殺してはいけない」という一文が、時として「どんな理不尽にも黙って耐えろ」というメッセージになってしまうことに、私は違和感を覚える。
この構図は、非常に巧妙だ。
・権力者や加害者的立場にいる人間が、道徳を盾にして反撃を封じる
・本当の意味で傷ついている側は、「倫理違反者」のレッテルを貼られ、声を上げることさえできなくなる
つまり、「殺してはいけない」の“絶対性”は、時として抑圧の道具として使われる。
ここに潜むのは、道徳という名の支配構造だ。
一見美しく見える価値観が、実は誰かを縛るための枷になっている。
まとめ
人を殺すな。それは、当たり前のことだ。
だがその「当たり前」が、常にすべての人に公平に作用しているかどうかは、慎重に見極める必要がある。
道徳も、法も、社会も──その多くは“力のある側”によって形作られている。
だからこそ私は、「絶対に殺しはいけない」という言葉に対して、盲目的に従うのではなく、立ち止まって考えたい。
それは果たして、すべての人のためにあるのか?
それとも、誰かを黙らせるための都合の良い言葉に過ぎないのか?
この問いは、ずっと胸の中に置いておきたい。


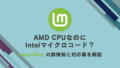
コメント